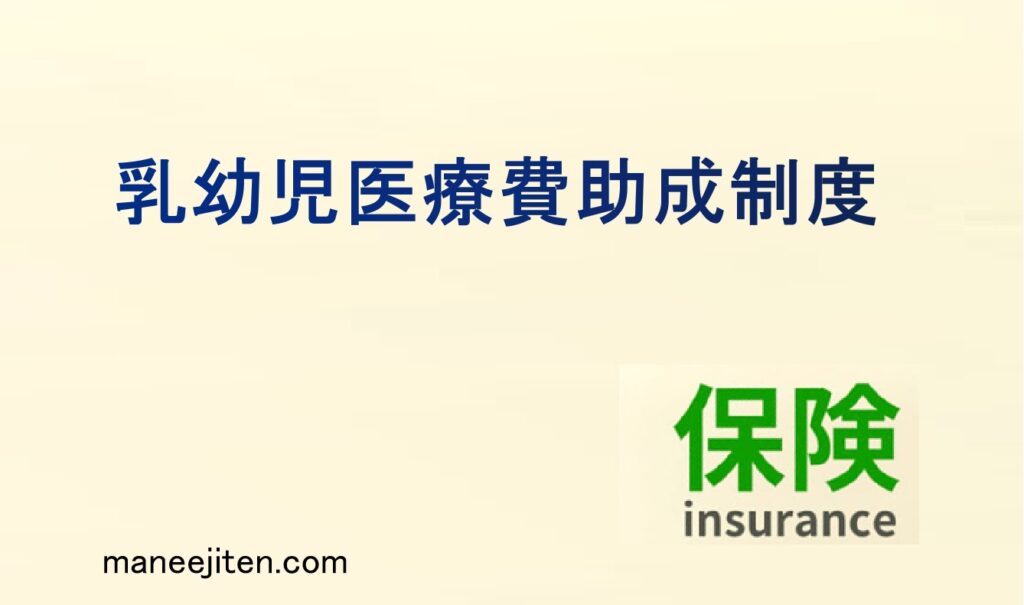子どもは病気やケガで病院にかかる機会が多いため、医療費の負担が家計にとって大きな悩みになりがちです。
そんな中、全国の自治体で導入されているのが「乳幼児医療費助成制度」です。
本記事では、この制度の基本的な仕組みから、対象年齢・自己負担のルール・自治体ごとの違いまで、初心者にもわかりやすく解説します。
乳幼児医療費助成制度とは?
乳幼児医療費助成制度とは、0歳から小学生や中学生といった子どもたちが安心して医療を受けられるように、自治体が医療費の自己負担分を一部または全額助成する制度です。
日本の公的医療保険では、原則として以下のように自己負担が決められています。
-
0歳~未就学児:医療費の自己負担は2割
-
小学生以上:大人と同じ3割負担
しかし、この制度を利用すれば、実際の医療費は「無料」あるいは「わずかな定額負担」で済む場合が多く、子育て世帯にとって大きな安心材料となります。
対象年齢は自治体ごとに異なる
厚生労働省の調査(平成25年4月1日現在)によると、全国すべての都道府県・市区町村で乳幼児医療費助成制度が実施されています。ただし、対象年齢や助成範囲は自治体によって異なるのが特徴です。
-
都道府県の制度:通院・入院ともに「就学前まで」を対象とするところが多い
-
市区町村の制度:通院・入院ともに「中学卒業まで」を対象とする自治体が最も多い
例えば、A市では「小学校卒業まで」が対象でも、隣のB市では「高校3年生まで助成」といった違いが見られます。
所得制限の有無
自治体によっては、制度利用に所得制限を設けています。
-
所得制限「あり」:保護者の所得が一定額を超えると助成対象外
-
所得制限「なし」:すべての子どもが助成の対象
共働きかどうか、扶養人数が何人いるかによっても判定が変わるため、必ず居住地の市区町村公式サイトで確認する必要があります。
まとめ
乳幼児医療費助成制度は、子育て世帯にとって大きな支援となる制度です。
-
自己負担割合は本来「2割~3割」だが、助成により無料や低額で受診可能
-
対象年齢は自治体によって「就学前まで」「中学卒業まで」など異なる
-
所得制限の有無も自治体ごとに違う
医療費は家庭の経済状況に直結するため、利用できる範囲を確認して賢く活用することが大切です。
さらに参照してください: