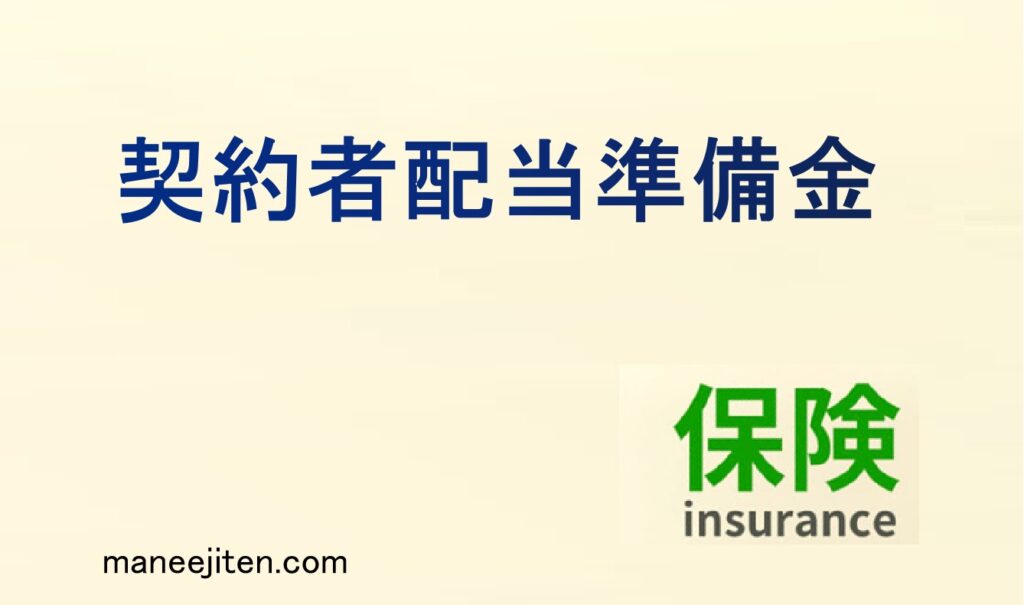生命保険に関する書類やパンフレットに出てくる「契約者配当準備金(けいやくしゃはいとうじゅんびきん)」という用語。
聞き慣れない言葉ですが、実は**保険会社が契約者に配当金を支払うための重要な“積立金”**のことを指します。
この記事では、契約者配当準備金の仕組みや役割について、生命保険の知識がない方でもわかるようにやさしく解説します。
✅ 契約者配当準備金とは?
契約者配当準備金とは、保険会社が契約者に配当金(=契約者配当金)を支払うために事前に積み立てておくお金のことです。
簡単に言えば、
「契約者に将来分配する配当金のために“準備”している資金」
というイメージです。
📌 配当金はどこから出てくるの?
生命保険の配当金は、保険会社の経営がうまくいったときに**剰余金(利益の余り)**から契約者に還元される仕組みになっています。
配当金の原資となる剰余金は、以下のような要因で生まれます。
-
実際の死亡者数が予定より少なかった
-
運用実績が予定利率を上回った
-
経費が予定より抑えられた など
これらの剰余金は、いったん「契約者配当準備金」として積み立てられ、そこから翌年度以降の配当にあてられるのです。
🧮 決算での流れ:契約者配当準備金が決まる仕組み
配当準備金は、保険会社の決算によって以下のような流れで決定されます。
-
剰余金の計算
予定と実績の差から生じた利益(剰余金)が算出されます。 -
前期の繰越剰余金と合わせる
前年度から繰り越された剰余金と合算。 -
総代会で繰入額を決定
株主総会にあたる「総代会」で、どれだけを契約者配当準備金として積み立てるか(=契約者配当準備金繰入額)が決まります。 -
配当率の決定と配当金の割り当て
繰入額に基づいて契約者配当率が算出され、契約内容に応じて契約者ごとに配当金が割り当てられます。
💡 具体的なイメージ:お弁当の取り分けに例えると?
ちょっとした例えで理解してみましょう。
-
剰余金:「お弁当を作ったら思ったより材料が安く済み、余った分」
-
契約者配当準備金:「余った材料を冷蔵庫にとっておいて、明日のお弁当に使おうと準備する」
-
配当金:「翌日、その材料を使って家族におかずとして振る舞う」
つまり、「余剰が出たらとりあえず準備金に回しておき、あとで分配する」という仕組みです。
🚫 注意点:準備金があっても配当は保証されない
契約者配当準備金があるからといって、必ずしも毎年配当金がもらえるわけではありません。
運用環境の悪化や保険会社の判断によっては、配当が少なくなったりゼロになったりすることもあります。
また、配当の有無に関係なく保障内容に影響はないため、「保険そのものの価値」が落ちるわけではありません。
📝 まとめ:契約者配当準備金は“配当金のタネ銭”
-
契約者配当準備金とは、将来の配当金支払いに備えて保険会社が積み立てる準備金。
-
決算で出た剰余金と前期からの繰越剰余金の中から、総代会で繰入額が決まる。
-
繰入額をもとに配当率が算出され、契約者に配当金として還元される。
-
必ずしも毎年配当がもらえるわけではなく、経済状況などにより左右される。
保険に加入するときは、配当の有無や金額に過度な期待をせず、保障内容をしっかり比較することが重要です。
さらに参照してください: