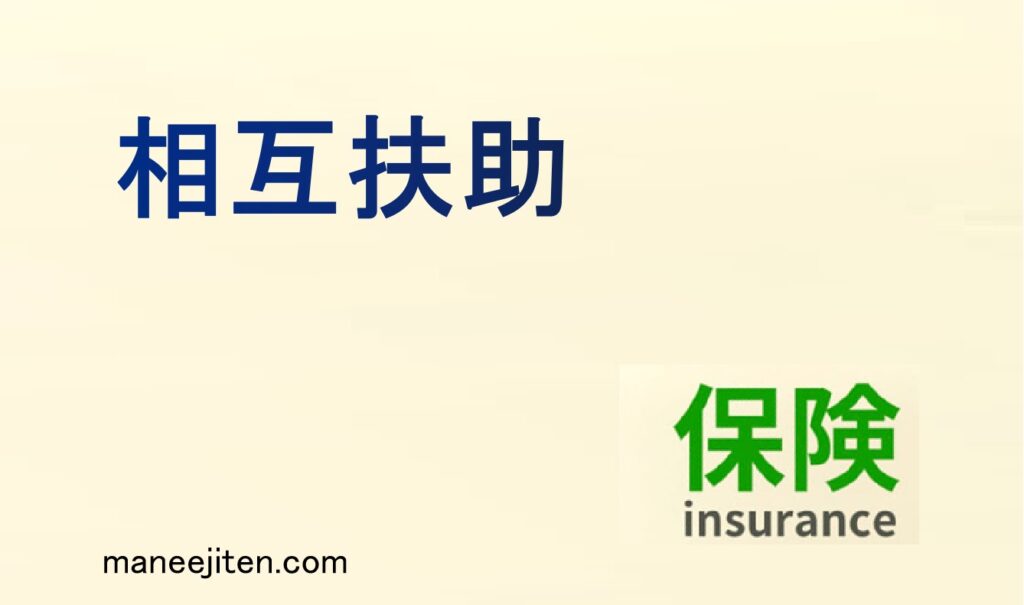保険の根本的な仕組みを一言で表すと、それは**「相互扶助(そうごふじょ)」**です。
簡単にいえば、「多くの人が少しずつお金を出し合い、困ったときに助け合う仕組み」のことです。
相互扶助の基本的な考え方
私たちは日常生活の中で、病気や事故、災害など、予測できないトラブルに直面する可能性があります。
こうした万一の事態が起こったとき、大きな金額が必要になることがありますが、一人でそのお金をすぐに用意するのは難しいものです。
そこで活躍するのが保険です。
保険では、多くの契約者があらかじめ一定の保険料を出し合い、そのお金を必要になった人へ支払います。
つまり「お互いを支え合う」ことで、もしものときの経済的負担を分散しているのです。
具体例でイメージしてみる
例えば100人が同じ保険に加入し、1人あたり年間1万円の保険料を支払うとします。
合計で100万円の資金が集まり、その年に病気や事故で大きな治療費がかかった人がいれば、その資金から保険金が支払われます。
こうすることで、一人ひとりの負担は小さくても、必要な人には十分な額を届けることができます。
公平性を守るためのルール「告知義務」
相互扶助は「みんなで助け合う」仕組みですが、公平性を保つためにはルールも必要です。
もし健康状態の悪い人が、何の制限もなく同じ条件で加入してしまうと、保険金の支払いが偏ってしまい、制度そのものが成り立たなくなります。
そこで生命保険では、契約時に**「告知義務」**があります。
これは、契約者や被保険者が現在の健康状態や過去の病歴などを正しく申告する義務のことです。
この情報をもとに、保険会社は契約を引き受けるかどうか、または条件をつけて契約するかを判断します。
まとめ
-
相互扶助は「多くの人が少しずつお金を出し合い、困ったときに助け合う仕組み」
-
保険はこの考え方をもとに成り立っている
-
公平性を守るために「告知義務」というルールがある
保険の根底には、この「相互扶助」という温かい助け合いの精神があります。加入するときは、この仕組みとルールをしっかり理解しておくことが大切です。
さらに参照してください: