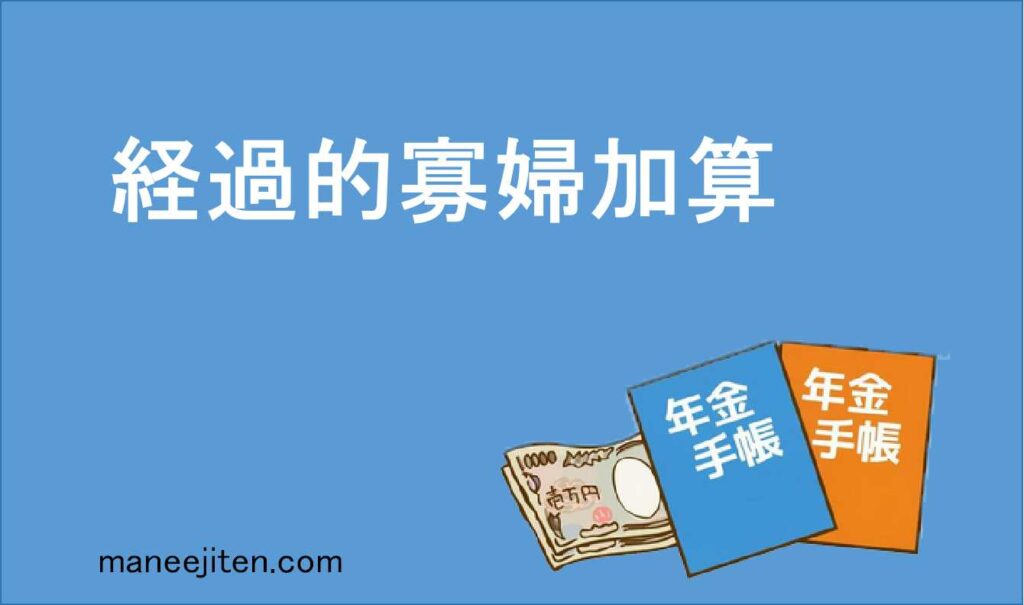配偶者を亡くされた後に受け取る 遺族厚生年金 には、状況に応じて「加算」がつく場合があります。
その一つが 経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん) です。
名前だけでは分かりにくい制度ですが、年金額を減らさないために設けられた大切な仕組みです。
本記事では、経過的寡婦加算の仕組み・対象者・注意点を分かりやすく解説します。
経過的寡婦加算とは?
経過的寡婦加算とは、65歳から受け取れる遺族厚生年金の上乗せ部分 です。
妻が遺族厚生年金を受けていて、65歳になったときに自分の 老齢基礎年金 を受け取り始めます。このとき、65歳までについては「中高齢寡婦加算」という仕組みで年金額を補填していましたが、65歳以降は中高齢寡婦加算がなくなります。
しかし、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算より少ないと、65歳になった途端に年金額が下がってしまいます。
そこで、その差を埋めるように調整するのが 経過的寡婦加算 です。
誰が対象になるの?
経過的寡婦加算を受け取れるのは、以下の条件に該当する方です。
-
遺族厚生年金を受けている妻
-
65歳になり、自分の老齢基礎年金を受け取り始めたとき
-
昭和31年(1956年)4月1日以前生まれで、国民年金加入可能な期間を満了している人を基準に額が設定されている
また、65歳以降になって初めて遺族厚生年金を受け始める妻も対象となるケースがあります。
どれくらいの額が加算される?
経過的寡婦加算の金額は一律ではなく、生年月日に応じて調整 されています。
昭和61年(1986年)4月1日時点で30歳以上だった人を基準とし、60歳まで国民年金にすべて加入したと仮定したときの 老齢基礎年金の額 に相当する金額を組み合わせて、ちょうど中高齢寡婦加算と同じ水準になるように設定されています。
つまり、「65歳前と後で年金額が急に下がらないようにするための調整給付」 という位置づけです。
注意すべきポイント
経過的寡婦加算には以下の制約があります。
-
障害基礎年金を受けている場合 は支給停止(ただし、障害年金が支給停止中なら除外)
-
加算額は個人の状況(生年月日や加入状況)により異なるため、必ず確認が必要
-
将来的に制度改正の影響を受ける可能性がある
まとめ
経過的寡婦加算は、
-
遺族厚生年金を受けている妻が65歳になるときに支給される
-
中高齢寡婦加算が終了した後も年金額を下げないための調整給付
-
生年月日や基礎年金額に応じて金額が決まる
という制度です。
遺族年金は生活に直結する大切な収入源です。ご自身が対象になるかどうか、またいくら支給されるのかは、年金事務所や「ねんきんネット」などで確認することをおすすめします。
さらに参照してください: