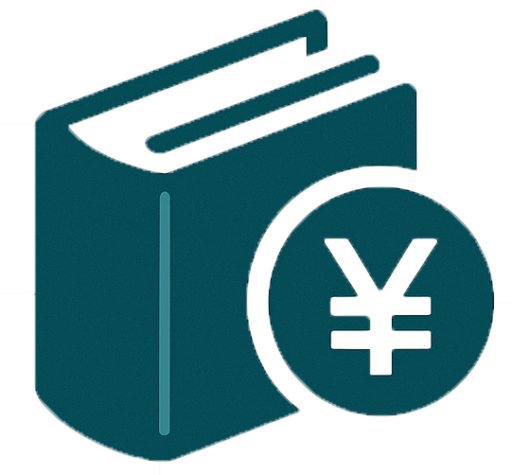企業の合併や再編では「吸収合併」「株式交換」など、さまざまな形があります。
その中でも少し特殊なのが「逆取得(ぎゃくしゅとく)」です。
一見すると小さな会社が大きな会社を“取得したように見える”このケースは、会計処理上も注意が必要な取引形態です。
逆取得とは
逆取得とは、吸収合併などの企業再編において、法律上の存続会社が消滅会社の株主に株式を交付した結果、消滅会社の株主が存続会社の議決権の過半数を握るようになった場合を指します。
つまり、法律上はA社がB社を吸収合併したように見えても、実際にはB社の株主がA社を支配するようになる状況です。
一般的な企業結合(通常の取得)では、存続会社が支配権を持ちますが、逆取得ではその関係が「逆転」します。
そのため「逆取得(reverse acquisition)」や「逆さ合併」と呼ばれることがあります。
逆取得の仕組みと考え方
逆取得は、見かけ上の企業関係と実質的な支配関係が入れ替わる点に特徴があります。
たとえば、業績や事業規模では大きいが非上場の会社が、上場している小規模会社を形式上「存続会社」として吸収合併するケースが挙げられます。
この場合、非上場会社(法的には消滅会社)が実質的に支配権を持つことになります。
つまり、「法的には消滅会社が実質上の存続会社になる」状態です。
この構造は、企業結合会計基準でも明確に定義されており、財務諸表の作成時には実質的な支配関係に基づいて処理を行う必要があります。
逆取得の主な目的とメリット
逆取得が行われる背景には、経営上のさまざまな狙いがあります。
一つは繰越欠損金の利用です。
業績が悪化していた企業の欠損金を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
もう一つは上場のためのコスト・期間の短縮です。
たとえば、非上場の大企業がすでに上場している小規模会社を逆取得することで、新たにIPO(株式上場)手続きを行わずに、上場企業としての地位を得ることができます。
このような方法は「裏口上場(backdoor listing)」と呼ばれることもあります。
逆取得の会計処理
逆取得の場合、会計上の「取得企業」と「被取得企業」は、法律上の存続・消滅関係と一致しません。
したがって、会計処理では「実質的に支配権を得た側(=法的には消滅会社)」を取得企業として扱います。
たとえば、A社(非上場・大企業)がB社(上場・小規模)を形式上吸収した場合、
法律上の存続会社はB社ですが、会計上の取得企業はA社となります。
このように、実態を優先して財務諸表を作成する点が、逆取得会計の大きな特徴です。
逆取得に関する法的根拠
逆取得の定義は、財務諸表等規則第八条第36号に規定されています。
この中では、以下のようなケースが逆取得に該当するとされています。
-
吸収合併により、消滅する企業が存続会社を取得すると考えられる場合
-
吸収分割会社や現物出資を行った企業が、承継会社または出資を受けた企業を取得すると考えられる場合
-
株式交換完全子会社が、株式交換完全親会社を取得すると考えられる場合
これらの規定は、実態に即した支配関係を会計上正確に反映させるために設けられています。
逆取得が行われる具体的なケース
例として、上場しているベンチャー企業B社と、非上場の大手IT企業A社が合併する場合を考えます。
A社は事業規模も技術力もB社より大きいものの、上場していません。
このとき、B社を法律上の存続会社とし、A社を吸収する形で合併を行うと、A社の株主が合併後の会社の議決権の大半を握ることになります。
この結果、形式上はB社がA社を吸収した形になりますが、実際にはA社が合併後の会社を支配しており、逆取得が成立します。
まとめ
逆取得とは、法律上の企業関係と実質的な支配関係が逆転する特殊な企業結合の形態です。
会計上は、実際に支配権を獲得した側を「取得企業」として扱う点が重要です。
上場の効率化や繰越欠損金の活用といったメリットもありますが、会計処理や税務上の判断が複雑になるため、専門家による慎重な検討が欠かせません。
逆取得は企業再編の中でも非常に興味深いテーマであり、会計上の実質主義を理解するうえで重要な事例といえるでしょう。
さらに参照してください: