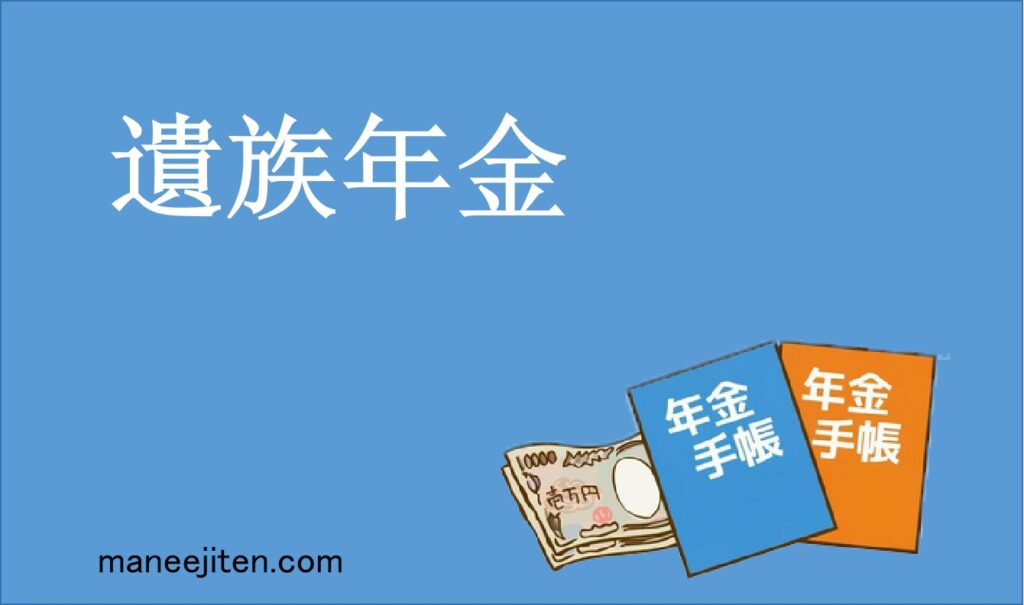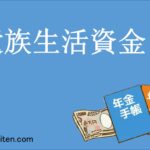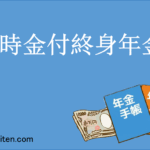「遺族年金(いぞくねんきん)」は、家計を支える大切な仕組みの一つです。
もしも一家の大黒柱など、家計を支えていた人が亡くなった場合、残された家族の生活を守るために支給されます。
公的年金制度の中でも、老後の年金とは別に「万が一の備え」として重要な役割を持っています。
ここでは、遺族年金の基本的な仕組みや種類、支給要件の概要を初心者向けにやさしく解説します。
✅ 遺族年金とは?
遺族年金とは、被保険者(公的年金に加入している人)が亡くなった際に、遺族の生活を保障するために支給される年金のことをいいます。
ポイントは以下の通りです。
-
遺族の生活の安定を目的とした公的制度
-
被保険者が生計を支えていた遺族に支給される
-
老後の年金(老齢年金)とは別の給付
たとえば、会社員の夫が亡くなり専業主婦と子どもが遺されるケースなどで、家計を支える仕組みとして非常に重要です。
✅ 遺族年金の3つの種類
日本の公的年金制度には、以下の3種類の遺族年金があります。
1️⃣ 遺族基礎年金
-
国民年金(基礎年金)の被保険者が亡くなった場合に支給
-
18歳到達年度の末までの子どもがいる配偶者、または子ども自身が対象
-
定額の支給(子どもの人数で加算あり)
例)小さな子どもを抱えた配偶者が受け取れる年金
2️⃣ 遺族厚生年金
-
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給
-
主に配偶者や子ども、場合によっては父母・孫も対象
-
被保険者の報酬に応じて支給額が変動
例)会社員の配偶者が亡くなった場合に支給
3️⃣ 遺族共済年金
-
公務員など共済組合に加入していた人が亡くなった場合
-
厚生年金に近い仕組みだが、共済組合独自の給付ルールもあり
-
現在は厚生年金と原則統合され、経過措置などが適用されるケースも
✅ 支給要件や受給資格は?
-
被保険者が一定の保険料納付要件を満たしている必要がある
-
受給対象者が「生計を維持されていた遺族」であること
-
年齢や子どもの有無などで受給資格が変わる
たとえば、子どもがいない場合には遺族基礎年金を受け取れないなど、細かい条件があります。
✅ 遺族年金の受給金額の目安
-
遺族基礎年金は定額制(子ども加算あり)
-
遺族厚生年金は被保険者の給与水準によって計算
-
遺族共済年金は基本的に厚生年金に準じつつ、経過措置などがある
具体的な金額は年金機構の試算ツールなどを使って計算可能です。
✅ まとめ
遺族年金は、突然の不幸で家計を失った遺族を支える大切な公的年金制度です。
✅ 基礎年金・厚生年金・共済年金の3種類がある
✅ 支給には条件や受給資格がある
✅ 家族構成や子どもの有無で受給額が変わる
「うちはもらえるの?」「どのくらい受け取れる?」と不安な方は、日本年金機構の公式サイトや年金事務所で詳細を確認することをおすすめします。
さらに参照してください: