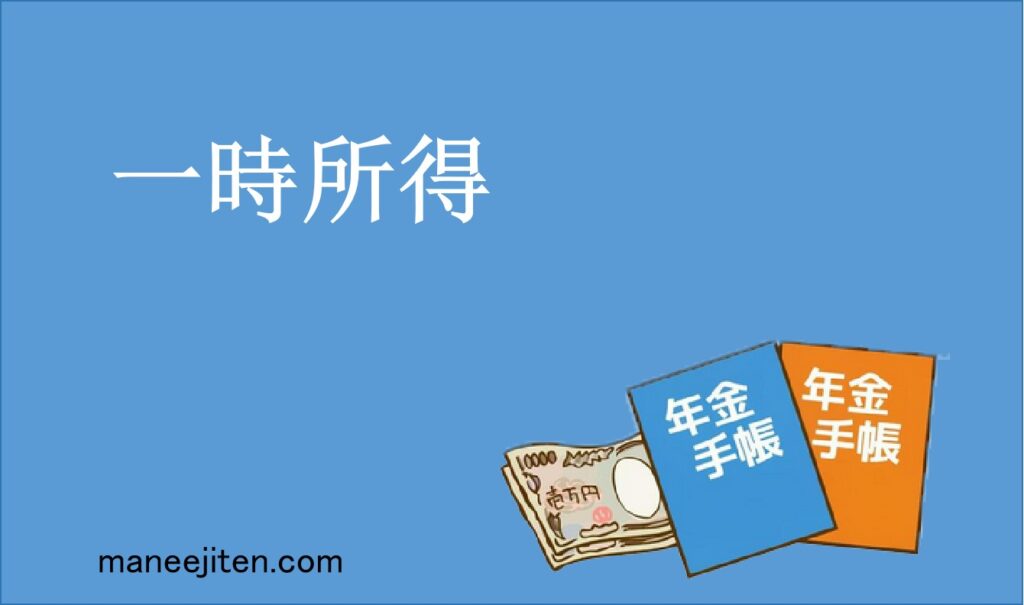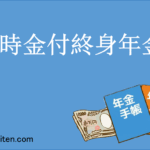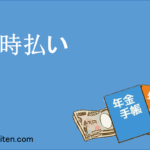「一時所得(いちじしょとく)」は、所得税の計算で重要な区分のひとつです。
言葉は難しく聞こえますが、実生活でも身近に発生するケースがあります。
この記事では、初心者にもわかるように、一時所得の意味、具体例、注意点を解説します。
一時所得の定義
一時所得とは、営利目的の継続的な行為から生じたもの以外の所得で、かつ労務(仕事の報酬)や資産の売却による対価ではない、一時的な所得を指します。
簡単に言えば、「継続して稼いでいるわけでもなく、働いた対価でもなく、たまたま得た臨時収入」と考えるとイメージしやすいでしょう。
一時所得に該当する具体例
税法上の代表的な「一時所得」には、以下のようなものがあります。
-
懸賞や福引きの賞金・賞品
-
例:テレビ番組の視聴者プレゼントで当選した10万円分の商品券
-
-
競馬・競輪などの払戻金
-
例:競馬で的中して得た50万円の配当
-
-
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
-
例:10年満期の生命保険を解約して受け取った返戻金
-
-
法人からの贈与
-
例:会社から個人への記念品や金品の贈呈
-
-
遺失物拾得者や埋蔵物発見者への報労金
-
例:拾った財布を警察に届け出て持ち主から受け取った謝礼
-
✅ ポイント
業務に関連する収入(仕事で得た謝礼や副業収入など)は一時所得ではなく、雑所得や事業所得に分類されます。
一時所得の課税方法
「一時所得」は課税対象になりますが、すべての金額がそのまま課税されるわけではありません。
① 計算式
② 具体例
たとえば懸賞で100万円を受け取った場合、経費が0円なら:
-
100万円 - 50万円(特別控除)= 50万円
-
50万円 ÷ 2 = 25万円(課税対象)
この25万円が所得に加算されます。
まとめ
「一時所得」は、偶然的・臨時的に得たお金を指し、働いた対価や資産売却による収入は含まれません。
懸賞の当選金、保険の満期返戻金、競馬の払戻金などが代表例です。
税金計算では50万円の特別控除や2分の1課税など優遇措置もありますが、高額当選などの場合は課税されるので注意しましょう。
さらに参照してください: