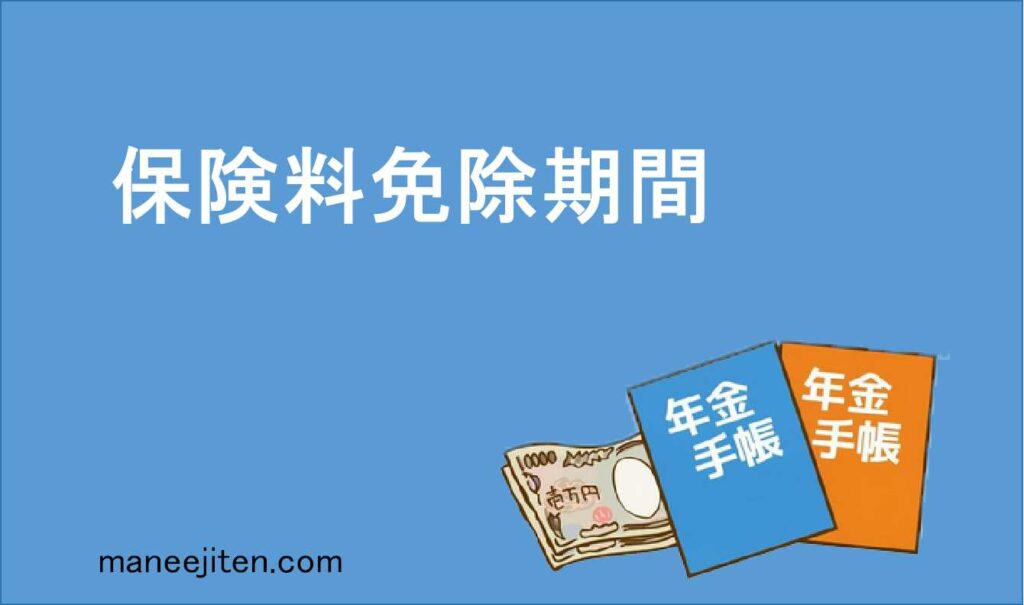国民年金に加入していると、経済的な事情や特定の条件によって 「保険料を納めなくてもよい期間(=保険料免除期間)」 が設けられることがあります。
この記事では、保険料免除期間の仕組み・種類・年金額への影響・追納のポイント を専門家の視点からわかりやすく解説します。
保険料免除期間とは?
「保険料免除期間」とは、国民年金の第1号被保険者として加入している期間のうち、保険料の納付が免除される期間 のことを指します。
この免除制度を利用すれば、経済的に厳しい状況でも将来の年金受給資格を確保することができます。
保険料免除の種類
保険料免除には、大きく分けて 2つのパターン があります。
-
法定免除
本人の状況に応じて、自動的に保険料が免除される制度。-
障害基礎年金の受給者
-
生活保護を受けている人
などが該当します。
-
-
申請免除
本人が申請し、所得などの条件を満たした場合に認められる免除。-
全額免除
-
4分の3免除
-
半額免除
-
4分の1免除
など、段階的に設定されています。
-
保険料免除期間と年金額の関係
保険料免除期間は、老齢基礎年金の「受給資格期間」には含まれる ため、将来の受給資格を失う心配はありません。
ただし、年金額の計算では納付した場合よりも少なくなります。
-
全額免除の場合:年金額に 2分の1(平成24年度以降) 反映
-
平成21年3月まで:3分の1 の反映
-
一部免除(4分の3免除・半額免除など)の場合は、納めた割合+国の負担分が反映
👉 つまり「免除を受けたままにする」よりも「追納する」ことで将来の年金額を増やすことができます。
追納(ついのう)で将来の年金額を増やす
免除された保険料は、10年前までさかのぼって追納することが可能 です。
追納することで、その期間は「全額納付」として扱われ、将来の年金額が増えます。
追納の注意点
-
追納には 時効(10年) がある
-
追納の時期によっては 加算金(延滞のようなもの) が発生することもある
-
家計に余裕が出たときに少しずつ追納するのがおすすめ
まとめ
-
保険料免除期間 は、経済的に厳しい時期でも将来の年金受給資格を守るための仕組み。
-
免除の種類は「法定免除」と「申請免除」に分かれる。
-
年金額には一部しか反映されないため、追納制度を活用することが重要。
-
追納できるのは 過去10年分まで。早めの対応が将来の年金額に直結する。
さらに参照してください: