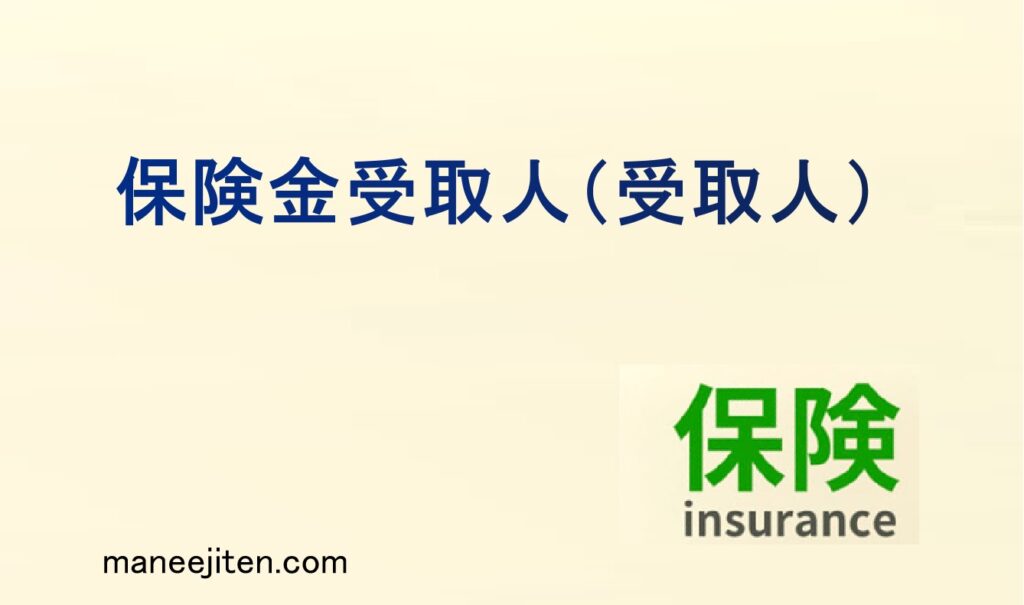生命保険や医療保険に加入するときに必ず出てくるのが「保険金受取人(受取人)」という言葉。
保険契約ではとても重要な役割を持つ存在ですが、いざ説明を聞くと「誰を指定すればいいの?」「途中で変えられるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、保険金受取人の基本的な意味、受取人の種類や指定の方法、変更の注意点をわかりやすく解説します。
保険金受取人とは?
保険金受取人とは、保険事故が起きたときに保険会社から保険金を受け取る人のことを指します。
受取人は、保険金の支払事由(死亡・入院・手術など)が発生した場合、保険会社に対して保険金の支払いを請求することができます。
保険の種類ごとの受取人
1. 医療保険・がん保険など(給付金)
入院や手術などの際に支払われる「給付金」は、通常被保険者本人が受け取ります。
例:がんで入院 → 入院給付金を本人が請求して受け取る。
2. 生命保険(死亡保険金)
死亡時に支払われる保険金は、保険契約者があらかじめ指定した「受取人」が受け取ります。
例:夫が契約者兼被保険者、妻を受取人に指定 → 夫が亡くなった場合、妻が死亡保険金を受け取る。
3. 満期保険金
満期を迎えた場合の保険金(満期保険金)は、契約者が指定した受取人が受け取ります。
契約者本人が受取人になるケースが一般的です。
保険金受取人は誰でも指定できる?
基本的には契約者の自由ですが、配偶者・子ども・親族など、法律上関係が明確な人を受取人に指定するのが一般的です。
保険会社によっては「赤の他人」を受取人に指定することはできない場合があります。これは、不正な目的での保険加入を防ぐためです。
途中で変更はできる?
保険金受取人は、契約途中でも契約者の申し出により変更が可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
-
契約者本人の同意が必須(受取人本人の同意は不要)
-
手続きには所定の書類提出が必要
-
保険会社によっては審査や確認が入ることもある
👉 例えば、結婚や離婚、出産などライフステージの変化に応じて、受取人を変更しておくことが大切です。
受取人をめぐるトラブル例
実際には、受取人の指定や変更をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。
-
離婚後に元配偶者を受取人のままにしてしまった
-
子どもを複数人指定せず、誰が受け取るのか不明確になった
-
契約者の意思と異なる形で受取人が放置されていた
こうしたトラブルを防ぐには、定期的に契約内容を確認し、必要に応じて受取人を変更することが重要です。
まとめ
-
保険金受取人とは、保険事故が発生した際に保険金を受け取る人。
-
医療保険などの給付金は被保険者本人、死亡保険金や満期保険金は契約者が指定した受取人が受け取る。
-
原則として契約者が自由に指定・変更できるが、配偶者や親族が一般的。
-
結婚や出産、離婚などライフイベントごとに見直すのがおすすめ。
さらに参照してください: