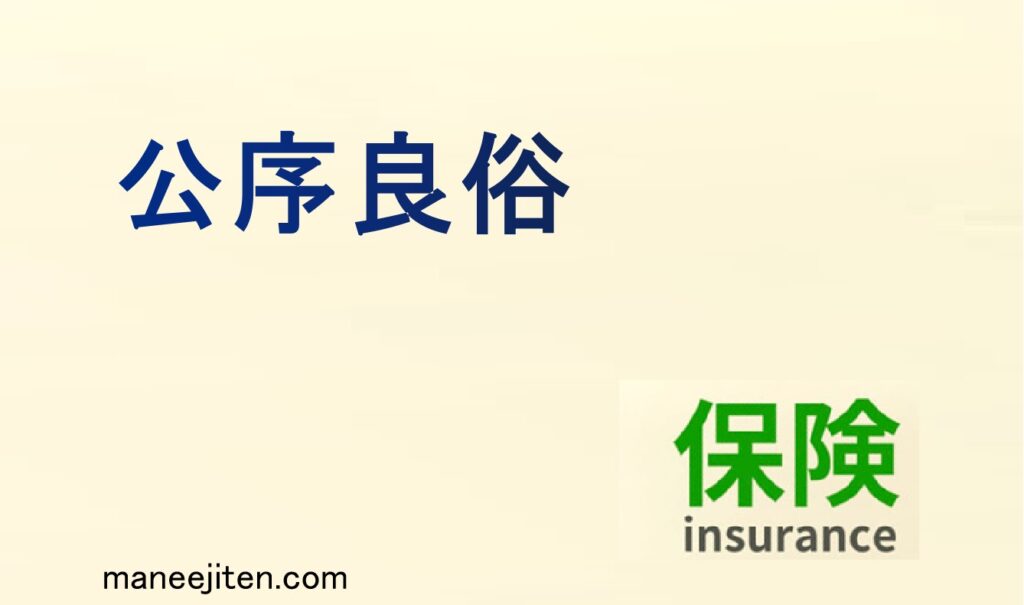「公序良俗(こうじょりょうぞく)」という言葉は、契約や法律に関する話題でよく登場しますが、「なんとなくイメージはあるけど、具体的に何が該当するのかよくわからない…」という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、公序良俗の意味や法律上の位置づけ、実際の判例で示された事例などを初心者にもわかりやすく解説します。
✅ 公序良俗とは?基本の意味と法的根拠
「公序良俗」とは、社会全体の一般的な利益や、社会通念上の道徳観・倫理観を指す言葉です。
読み方は「こうじょりょうぞく」。
民法第90条では、以下のように規定されています:
民法第90条
「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」
つまり、社会の秩序や倫理に反するような契約や約束は、法的に効力を持たないというルールがあるのです。
🧾 なぜ「公序良俗」が必要なの?
契約は原則として、当事者同士が自由に内容を決められる「契約自由の原則」が基本です。
しかし、もしその自由を悪用して、社会的に望ましくない内容の契約が成立してしまうと、個人の権利や社会全体の秩序が損なわれてしまうおそれがあります。
そこでストッパーとして設けられているのが、この「公序良俗」という考え方です。
📌 判例にみる公序良俗に反する行為の分類と具体例
過去の裁判で無効と判断された行為は、以下のように分類できます。
1. 人倫に反する行為
例:既婚者との婚約契約
結婚しているにもかかわらず他人と婚約した場合、その婚約契約は「人としての倫理に反する」として、公序良俗違反で無効と判断される可能性があります。
2. 正義の観念に反する行為
例:賭博行為
違法な賭け事に関連する契約や報酬の取り決めは、たとえ双方が合意していても、法律上は無効とされる可能性が高いです。
3. 個人の自由を極度に制限する行為
例:芸娼妓契約(身売り契約)
過去には、女性が自由を奪われて働かされる「芸娼妓契約」が問題になりました。現在では明確に公序良俗に反するとされ、すべて無効です。
4. 暴利行為
例:過度な違約金や高利貸し契約
借金返済の遅延に対して、常識を逸した違約金や金利を設定していた場合、「暴利行為」として無効とされることがあります。
⚖ 公序良俗違反になるかどうかの判断基準は?
「これが公序良俗違反かどうか」は、その契約がなされた時点の社会常識や倫理観を基準に判断されます。
つまり、時代や社会の価値観の変化によって、公序良俗の判断も変わりうるということです。
✅ ポイントは以下のとおり:
-
社会全体の倫理観に反していないか?
-
個人の人権や自由を不当に制限していないか?
-
法律で明確に禁止されていないか?
-
双方の立場に著しい不公平がないか?
🧑💼 実務での注意点|保険や契約の場面でも無効になる?
保険契約や不動産取引など、一見すると合法に見える契約でも、公序良俗に反すれば無効とされる可能性があります。
たとえば:
-
虚偽の申告を前提とした保険契約
-
極端に高額な解約手数料を定めた契約
-
労働者を不当に拘束する誓約書
なども、内容次第では「無効」と判断されかねません。
✅ まとめ|「合意したから有効」とは限らない
契約は自由ですが、それは社会的なルールや道徳の上に成り立つものです。
「お互いが納得しているから問題ない」と思っていても、その内容が社会通念に反していれば、公序良俗違反として無効になる可能性があります。
ビジネスや個人間の契約においても、「この内容は社会的に妥当か?」という視点を常に持っておくことが大切です。
さらに参照してください: