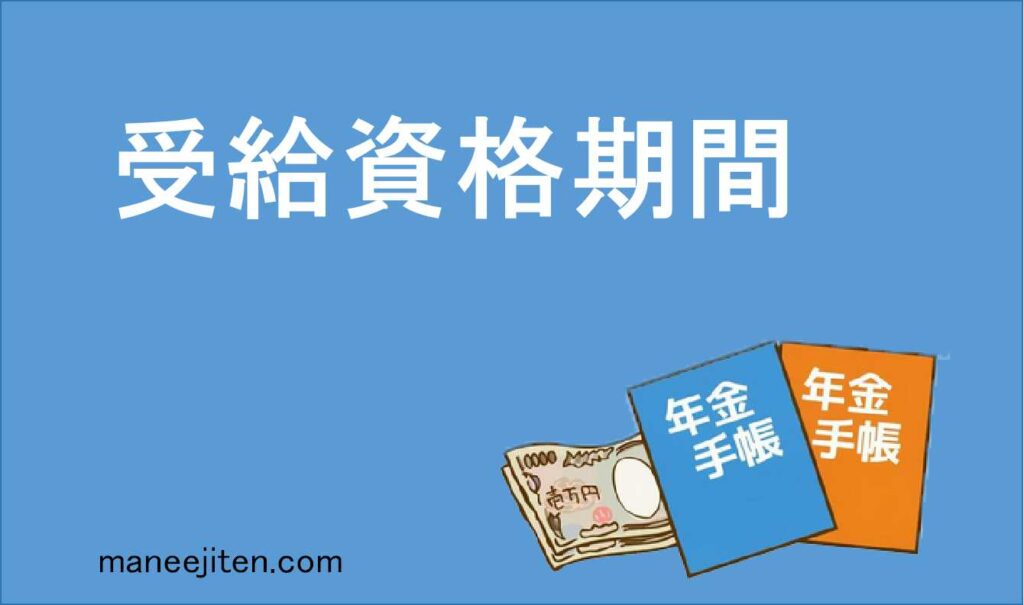年金を受け取るには、一定の加入期間が必要です。
この加入期間を満たしていないと、老齢年金や障害年金を受け取れません。
今回は、年金の「受給資格期間」について、初心者にもわかりやすく解説します。
受給資格期間とは?
受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な保険料を納めた期間や加入者であった期間の合計です。
簡単に言うと、「年金をもらう資格を得るために最低限必要な期間」のことです。
日本の公的年金における基本ルール
-
老齢基礎年金の場合
→ 受給資格期間は10年間(120か月)が基本です。 -
対象期間
-
国民年金の加入期間
-
厚生年金や共済組合の加入期間
-
保険料免除期間や、年金額に反映されない合算対象期間も含まれます
-
例:国民年金で5年間、厚生年金で5年間加入していれば、合計10年間となり受給資格を満たします。
受給資格期間に含まれる期間
-
保険料を納めた期間
-
月単位で支払った国民年金や厚生年金の期間
-
-
保険料が免除された期間
-
経済的事情などで免除された期間も対象
-
-
合算対象期間
-
学生期間や特定の国民年金加入期間など、年金額には反映されないが資格期間として扱われる期間
-
ポイント:受給資格期間は「年金額」とは別に考える必要があります。資格を満たせば受給可能ですが、金額は加入期間や保険料額によって変わります。
受給資格期間を満たしていない場合
-
受給資格期間が10年に満たない場合、老齢基礎年金を受け取れません。
-
この場合、加入期間を追加したり、免除期間を申請して資格を満たす方法があります。
まとめ
-
受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な最低加入期間です。
-
日本の公的年金では、老齢基礎年金の受給資格期間は10年間が基本です。
-
国民年金、厚生年金、共済組合の期間、免除期間、合算対象期間などが含まれます。
-
受給資格期間を確認し、年金を無駄なく受け取ることが大切です。
さらに参照してください:
準確定申告とは?年金受給者の死亡後に必要な手続きをわかりやすく解説
Visited 38 times, 2 visit(s) today