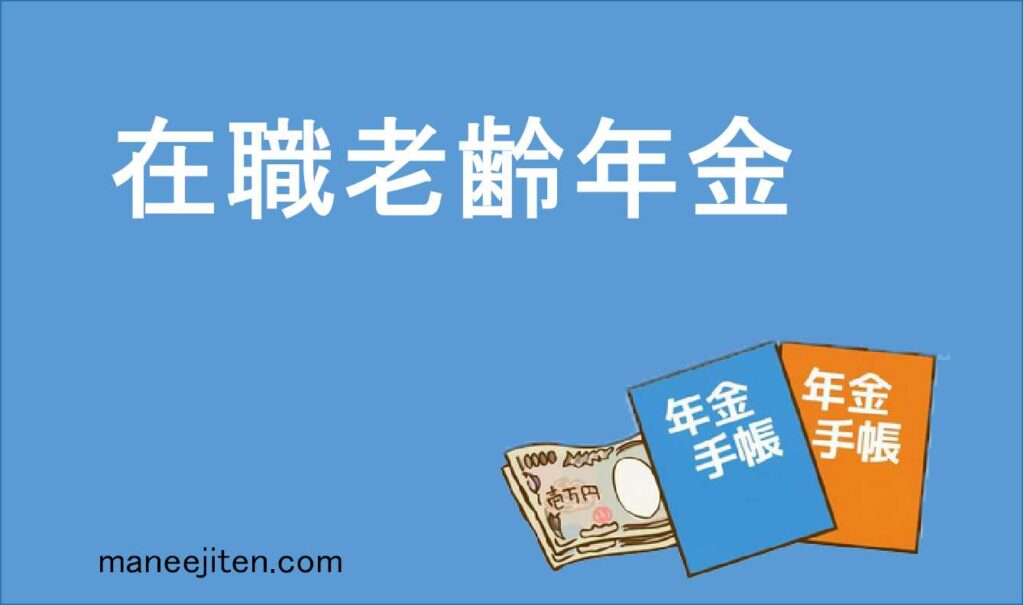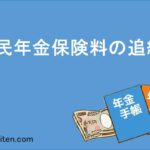60歳以降に働きながら受け取る老齢厚生年金を「在職老齢年金」といいます。
賃金と年金額によっては、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
この記事では、在職老齢年金の仕組みや計算方法、注意点を解説します。
在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金は、60歳以降に厚生年金保険に加入しながら受ける老齢厚生年金です。
年金額と賃金の合計が一定額を超える場合、超過分の半額が年金から支給停止されます。
令和7年度の調整額では、合計51万円を超える部分が対象です(※老齢基礎年金は全額支給されます)。
支給停止の変遷と対象
-
平成16年(2004年)改正前:老齢厚生年金の2割相当額を基準に支給停止が算出されていました。
-
平成17年(2005年)4月以降:60歳台前半の就労を阻害しないため、この算出方法は廃止されました。
-
平成27年(2015年)10月以降:70歳以上や議員、共済組合加入者も支給停止の対象となります。
70歳以降も、平成16年の改正により同様の取り扱いが行われますが、保険料負担はありません。
計算例(令和7年度)
令和7年度の支給停止調整額は以下の通りです。
-
賃金+年金額 = 60万円の場合
→ 51万円を超える9万円の半額4.5万円が支給停止
→ 実際に受け取れる年金額は元の年金額 − 4.5万円
具体的な計算式や過去の支給停止の扱いについては、「令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金による年金支給月額の計算式」を参照するとわかりやすいです。
注意点
-
在職中の賃金と年金額によって支給停止額が変動します。
-
老齢基礎年金は全額支給され、支給停止の対象にはなりません。
-
過去の支給停止制度や改正内容を確認することが重要です。
まとめ
在職老齢年金は、60歳以降に働きながら受け取る老齢厚生年金で、賃金と年金額に応じて一部が支給停止される場合があります。
過去の改正や年齢による取り扱いの違いを理解することで、年金受給計画を立てやすくなります。
自分の賃金や年金額に応じて、支給停止額を事前に計算して、ライフプランに活かすことが大切です。
さらに参照してください: