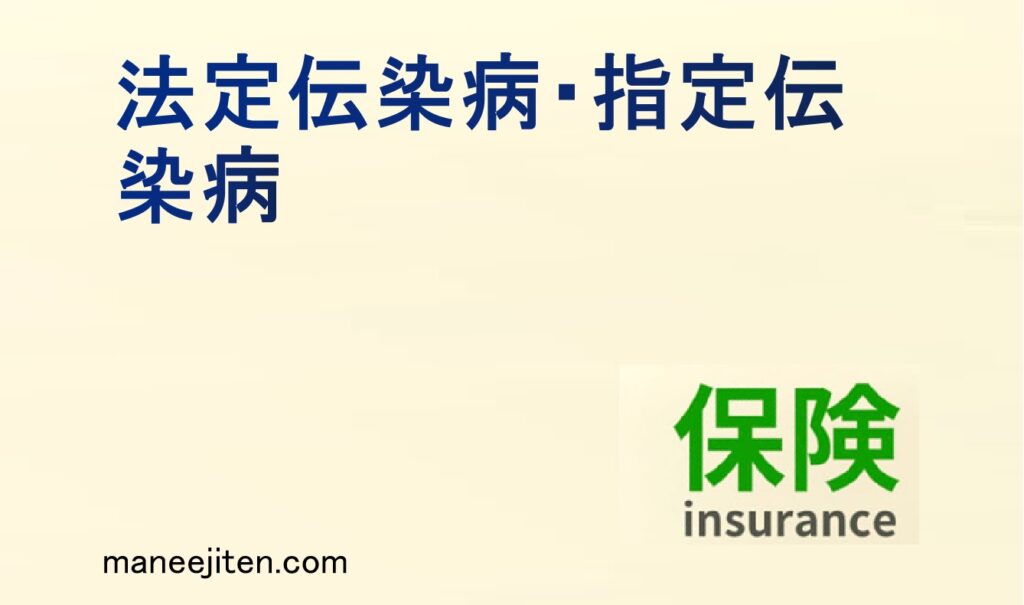「法定伝染病(ほうていでんせんびょう)」や「指定伝染病(していでんせんびょう)」という言葉は、保険の約款や医療関連ニュースで目にすることがあります。
しかし、現在では法律の改正により制度の名称や分類が変わっているため、混乱しやすい用語のひとつです。
この記事では、法定伝染病と指定伝染病の違い、さらに保険との関わりについてわかりやすく解説します。
法定伝染病・指定伝染病とは?
「法定伝染病」「指定伝染病」は、かつての伝染病予防法(平成11年3月に廃止)や、その後の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき定められていた分類です。
法定伝染病(11種類)
国が特に危険度の高い伝染病として定めていた疾病です。
-
コレラ
-
赤痢(疫痢を含む)
-
腸チフス
-
パラチフス
-
発疹チフス
-
猩紅熱(しょうこうねつ)
-
ジフテリア
-
流行性脳脊髄膜炎
-
ペスト
-
日本脳炎
-
痘そう
指定伝染病(3種類)
法定伝染病に準じて、一定期間「指定」された疾病です。
-
急性灰白髄炎(ポリオ)
-
ラッサ熱
-
腸管出血性大腸菌感染症(O157など)
感染症とは?
感染症とは、ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入し、増殖して症状を引き起こす病気を指します。
代表的な症状には、発熱、下痢、発疹、倦怠感などがあります。
感染経路はさまざまで、
-
人から人へ:飛沫感染や接触感染
-
動物や昆虫から:狂犬病、マラリアなど
-
食べ物から:食中毒など
があります。
現在の分類との違い
平成11年(1999年)に「伝染病予防法」が廃止され、現在は「感染症法」による1類〜5類感染症や新型インフルエンザ等感染症などの分類が用いられています。
そのため、法定伝染病・指定伝染病という言葉は、現在の法律上は使われません。
ただし、古い保険契約や約款ではいまだにこの用語が記載されていることがあります。
法定伝染病・指定伝染病と保険の関係
生命保険や医療保険の約款には、かつて「法定伝染病・指定伝染病」が給付対象かどうかを明記していたケースがありました。
そのため、古い契約をお持ちの方は、給付の対象となるかを確認する際に「特定感染症に該当するかどうか」で判断される場合があります。
👉 ポイント
-
新しい契約では「感染症法」に基づいた表現が多い
-
昔の契約では「法定伝染病・指定伝染病」と明記されていることがある
-
疑問がある場合は、保険会社や専門家に確認するのが安心
まとめ
-
法定伝染病・指定伝染病とは、旧・伝染病予防法に基づく感染症の分類
-
現在は「感染症法」により、1類〜5類感染症などに整理されている
-
古い保険契約では「法定伝染病」「指定伝染病」と記載されているため、給付の対象確認に必要になることがある
相続や年金と同様、保険の約款も法律改正の影響を受ける分野です。
特に古い保険に加入している方は、一度契約内容を見直し、必要なら保険会社や専門家に相談してみると安心です。
さらに参照してください: