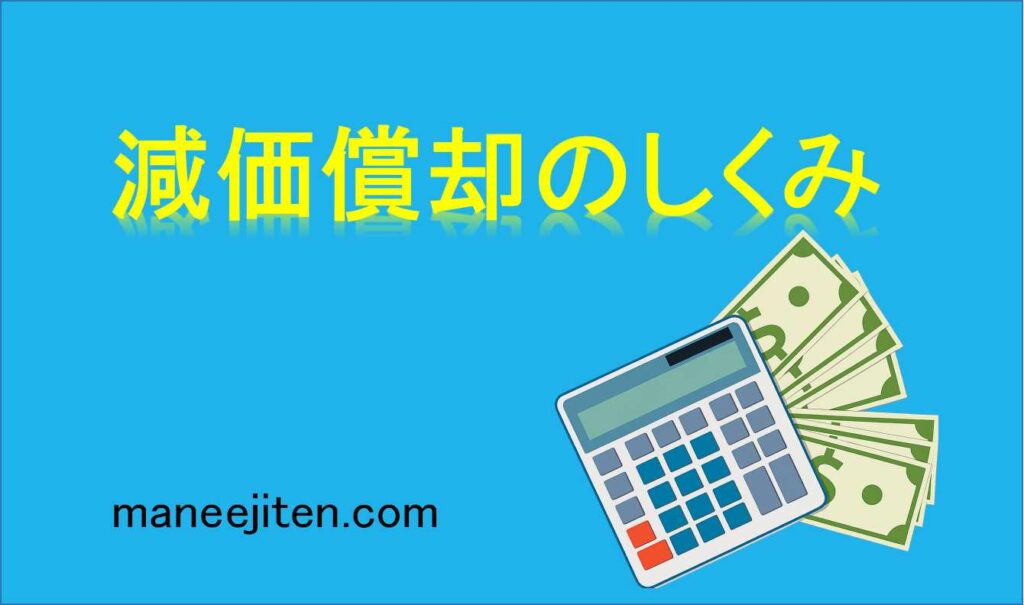企業の会計処理で欠かせない「減価償却」。
建物や機械、パソコンなどの資産は、時間の経過とともに価値が下がっていくため、その減少分を「費用」として計上する必要があります。
本記事では、減価償却の基本的な考え方から、計算方法、仕訳の仕方までを税理士監修のもとでわかりやすく解説します。
減価償却とは?
減価償却とは、資産を取得した際の総額を、使用できる期間(耐用年数)にわたって少しずつ費用として配分していく会計処理です。
たとえば、100万円の機械を10年間使う場合、毎年10万円ずつ費用計上するのが「定額法」による減価償却です。
資産は購入した時点で一度に価値を失うわけではありません。
実際には数年にわたり収益を生み出すため、その使用期間に応じて費用を分配するのが合理的です。これが減価償却の目的です。
なぜ減価償却が必要なのか
減価償却の目的は「費用と収益の対応関係」を正しく保つことです。
もし資産の取得費用を全額その年に計上してしまうと、実際の収益との対応が取れず、正しい利益が算出できません。
減価償却を行うことで、資産が生み出す収益と、それに対応する費用を一致させ、期間損益を適正に示すことができます。
また、減価償却を行わないと法人税や所得税の計算に影響が出ます。
特に法人の場合、減価償却費として損金算入できる金額は税法で上限が決まっており、償却を怠ると課税所得が増えて税負担が重くなります。
減価償却できる資産・できない資産
減価償却できるのは、時間の経過や使用によって価値が減少する資産です。
【減価償却できる主な資産】
-
建物、建物附属設備(照明・配管など)
-
機械装置、車両、工具、器具備品
-
ソフトウェア、特許権などの無形固定資産
【減価償却できない資産】
-
土地(使用によって価値が減らないため)
-
古美術品・出土品など希少価値があり、時の経過で価値が下がらないもの
-
建設中の建物や未使用の資産(事業供用前)
減価償却の基本用語
減価償却費
減価償却によって各年度の費用として計上される金額です。会計上は「減価償却費」として損益計算書に記載されます。
減価償却累計額
これまでに計上された減価償却費の累計額を示す勘定です。貸借対照表上では「固定資産の取得原価」から控除されます。
耐用年数
資産が通常の使用で効果を発揮できる期間です。国税庁が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で業種・用途別に定めています。
取得価額
資産の購入代金だけでなく、運搬費・設置費・関税など、使用可能な状態にするまでのすべての費用を含みます。
事業供用日
その資産を事業で実際に使用し始めた日です。取得日ではなく、この供用日から減価償却を開始します。
減価償却の計算方法
減価償却には主に3つの方法があります。
1. 定額法
毎年同じ金額を費用として計上する方法。安定的に償却費を計上できます。
計算式:
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
2. 定率法
毎年の未償却残高に一定の率を掛けて計算する方法。初年度に多く、年々少なくなる特徴があります。
計算式:
減価償却費 = 期首残高 × 定率法の償却率
3. 生産高比例法
製品の生産量や使用回数など、実際の稼働量に応じて減価償却費を計上する方法です。工場設備などに用いられます。
減価償却費の仕訳例
定額法(間接法)の場合
建物を1,000万円で取得し、耐用年数20年、償却率0.05の場合:
毎期の仕訳は次の通りです。
借方:減価償却費 500,000円
貸方:建物減価償却累計額 500,000円
このように、間接法では資産の原価を直接減らさず、累計額を別勘定として管理します。
減価償却と決算書の関係
減価償却は損益計算書と貸借対照表の両方に関わります。
-
損益計算書では「減価償却費」として営業費用に計上
-
貸借対照表では「固定資産」から「減価償却累計額」を差し引いた純額が表示
また、減価償却はキャッシュフローには直接影響しません。現金支出を伴わない「非現金費用」ですが、利益を調整するうえで非常に重要な項目です。
減価償却の注意点
-
耐用年数は業種や資産の種類ごとに異なります。国税庁の「耐用年数表」で必ず確認しましょう。
-
期中での取得・廃棄の場合は月割計算が必要です。
-
中小企業は少額償却資産の特例があり、30万円未満の資産は一括で費用処理できる場合があります。
まとめ:減価償却の基本を理解して正しい会計処理を
減価償却は、企業の利益計算や税務申告に欠かせない重要な会計処理です。
資産の価値を正しく費用化することで、経営状況をより正確に把握でき、税務リスクを避けることも可能になります。
減価償却の仕組みや計算方法を正しく理解し、決算書や固定資産管理に活かしていきましょう。
さらに参照してください: