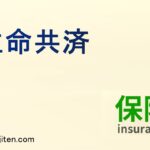生命保険に興味がある方や、加入を検討している方の中には、「生命表(せいめいひょう)」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。
保険会社が保険料を決めるときに使う、重要な統計データの一つです。
この記事では、「生命表ってなに?」「どんなふうに使われるの?」といった疑問に、初心者にもわかりやすくお答えします。
🔍 生命表とは?
生命表とは、ある年に生まれた10万人の新生児が、年齢を重ねるごとに何人生き残り、何人が亡くなるかを年齢別死亡率に基づいて示した統計表のことです。
別名「死亡表(しぼうひょう)」とも呼ばれており、厚生労働省などの公的機関や、生命保険会社などで活用されています。
📊 生命表の仕組みと主な項目
生命表には、以下のような項目が年齢ごとに記載されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| lx | 生存数:ある年齢まで生きている人の数(基準は出生時10万人) |
| dx | 死亡数:その年齢で死亡する人数 |
| qx | 死亡率:ある年齢で亡くなる確率 |
| ex | 平均余命:その年齢の人があと何年生きられるかの平均値 |
このような指標により、たとえば「50歳男性があと何年生きられる可能性があるか」「70歳までに何人が生存しているか」といった予測ができます。
🧮 生命保険と生命表の関係
生命保険会社では、保険商品を設計する際に「予定死亡率」を使います。この予定死亡率のベースとなるのが「生命表」です。
保険料の計算に使われる「三利源(さんりげん)」と呼ばれる3つの予定率:
-
✅ 予定死亡率(死亡リスクの予測)
-
✅ 予定利率(運用による利回りの見込み)
-
✅ 予定事業費率(事務コストの見積もり)
このうち、予定死亡率は性別や年齢ごとに生命表をもとに算出され、死亡保険のリスク評価に重要な役割を果たします。
💡 生命表の具体例:平均寿命と生存率
例えば、2020年の簡易生命表によると、日本人の平均寿命は次のようになっています。
-
男性:約81.6歳
-
女性:約87.7歳
また、同じ表からは「60歳男性の約92%が65歳まで生存する」といった統計も読み取れます。
こうしたデータは、年金設計や医療制度、保険商品の開発など、さまざまな分野で活用されています。
🏥 生命表は保険以外でも使われる
生命表は保険業界だけでなく、以下のような場面でも活用されています。
-
🔹 国や自治体の人口統計・高齢化対策
-
🔹 医療・介護政策の設計
-
🔹 年金制度の見直し
-
🔹 経済・保健研究の基礎データ
まさに**「いのち」と「社会」を見つめる統計の出発点**ともいえる存在です。
✅ まとめ|生命表は保険の“根拠”となるデータ
「生命表(せいめいひょう)」は、保険会社が科学的・統計的根拠に基づいて保険料を設定するための重要な資料です。
そこに記載されている死亡率や生存率のデータは、個人の人生設計や社会制度にも大きく関わっています。
生命保険をより深く理解するためにも、生命表の存在と役割を知っておくことはとても有益です。
さらに参照してください: