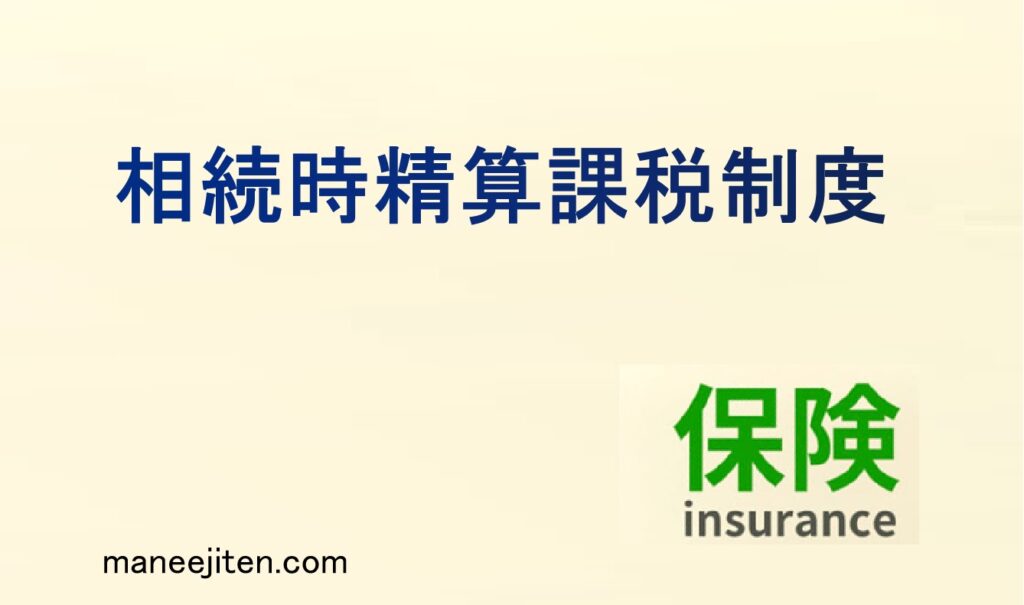相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど) とは、原則として60歳以上の父母または祖父母が、20歳以上の子や孫に対して行う財産の贈与に適用できる特例制度です。
この制度を利用すると、2,500万円までの贈与は非課税となり、超えた分には一律20%の贈与税が課税されます。
制度の基本ルール
-
贈与者の条件
60歳以上の父母または祖父母 -
受贈者(贈与を受ける人)の条件
20歳以上の子または孫(※2022年4月以降は18歳以上が対象) -
非課税枠
合計2,500万円まで贈与税がかからない
(超過額は一律20%課税)
利用する際の手続き
この制度を選択する場合、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに、税務署へ贈与税申告書と必要書類を提出します。
提出をしないと、この特例は適用されません。
相続時にどう扱われるのか?
「相続時精算課税」という名前の通り、制度を使って贈与を受けた財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産として再計算されます。
具体的には、贈与時の時価を相続財産に加算し、その合計額に基づいて相続税が算出されます。
事例でイメージ
例:
祖父(70歳)が孫(20歳)に1,000万円を贈与。
さらに翌年、孫に2,000万円を贈与。
→ 合計3,000万円の贈与となり、非課税枠2,500万円を超えた500万円に一律20%(100万円)の贈与税がかかります。
その後、祖父が亡くなった場合、贈与時の時価3,000万円が相続財産に加算され、相続税の計算対象になります。
メリットと注意点
メリット
-
生前にまとまった財産を移転できる
-
将来の相続税対策として活用可能
注意点
-
一度選択すると暦年課税(年間110万円まで非課税)に戻せない
-
贈与時の時価で相続財産に加算されるため、節税効果が限定的な場合もある
-
手続きや申告を忘れると適用できない
まとめ
-
相続時精算課税制度は、生前贈与を活用しやすくする制度だが、相続時に精算される仕組み
-
非課税枠は2,500万円まで、超過分は20%課税
-
適用には申告が必須で、一度選ぶと取り消せない
この制度は相続税対策の一環として有効な場合がありますが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。適用を検討する際は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。
さらに参照してください: