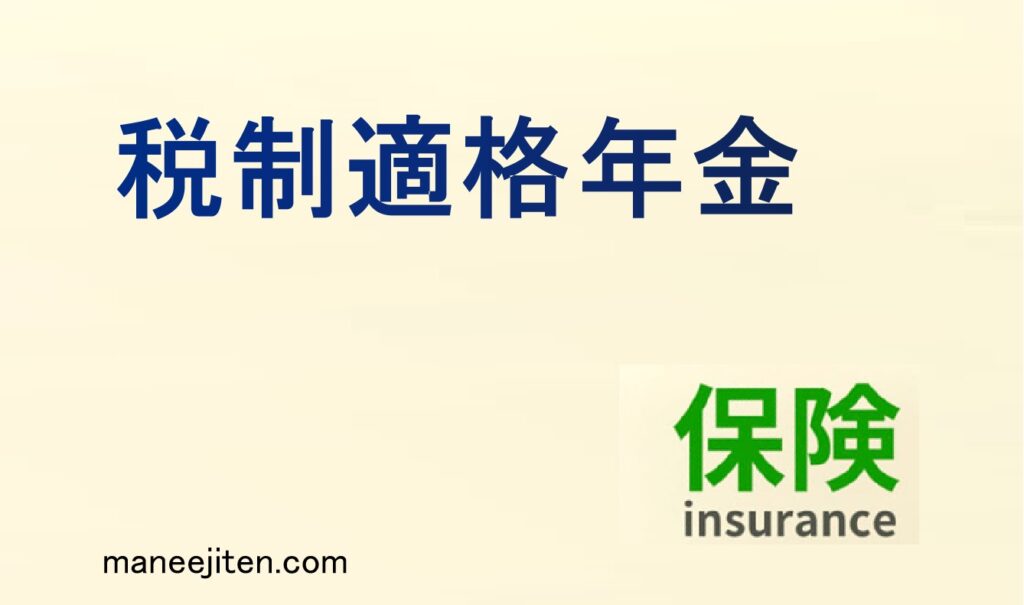「税制適格年金って、今もある制度なの?」
こんな疑問を持った方も多いのではないでしょうか。
かつて多くの企業が採用していた「税制適格年金(ぜいせいてきかくねんきん)」は、現在は新規導入ができない制度となっています。
この記事では、税制適格年金の意味や仕組み、なぜ廃止されたのか、そして現在の企業年金制度との違いについて、初心者にもわかりやすく解説します。
✅ 税制適格年金とは?
「税制適格年金」とは、企業が従業員の退職後の生活保障のために、年金資産を外部に積み立てる制度のことです。税制上の優遇措置が受けられることから、かつては中小企業を中心に幅広く利用されていました。
別名:
-
適格退職年金
-
適格年金
-
適年(てきねん)
💡 どんな制度だったの?
税制適格年金は、厚生年金とは別に企業が自主的に運用する退職年金制度として設けられていました。
特徴:
-
従業員が退職後に受け取る年金を目的とする
-
年金資産は生命保険会社や信託銀行などの外部機関に積み立て
-
企業が掛金を拠出
-
税制上の優遇措置あり(掛金は損金算入、受取時も一部非課税)
しかしながら、制度運用に関する規制が緩く、財政悪化リスクが高いという課題もありました。
🛑 税制適格年金は現在どうなっている?
2002年の「確定給付企業年金法」施行により、新たな税制適格年金の導入は認められなくなり、制度は廃止されました。
廃止の背景:
-
制度の透明性や健全性への懸念
-
年金資産の管理が不十分な事例の発生
-
厚生年金基金制度や企業型確定拠出年金などの整備による制度再編
そのため、企業は既存の税制適格年金を**「確定給付企業年金」や「企業型確定拠出年金」などの他制度へ移行**することが求められました。
🔁 移行先としての確定給付企業年金(DB)とは?
税制適格年金の移行先として最も多かったのが「確定給付企業年金(DB)」です。
DB(確定給付型)の特徴:
-
退職後にあらかじめ決められた年金額を受け取れる
-
運用リスクは企業側が負担
-
税制面でも優遇あり(従来の税制適格年金の仕組みを継承)
👨🏫 事例:中小企業が抱えた移行の課題
例えば、ある従業員数50名の製造業では、長年税制適格年金を運用してきました。
しかし、法改正により制度廃止が決定し、移行先を検討する中で**「確定拠出年金(DC)」では従業員の運用負担が大きすぎる**と判断。
最終的に、既存の資産を引き継ぎつつ給付額の安定性がある「確定給付企業年金」へ移行しました。
このように、制度の選択は企業の体力や人材構成によって大きく異なります。
📌 まとめ|税制適格年金は“過去の制度”だが重要な知識
-
税制適格年金は、企業が従業員の退職後の年金を外部積立する制度
-
税制上の優遇措置があり、かつては広く活用されていた
-
2002年の法改正により廃止され、現在は新規導入できない
-
現在は確定給付企業年金などへの移行が進んでいる
さらに参照してください: