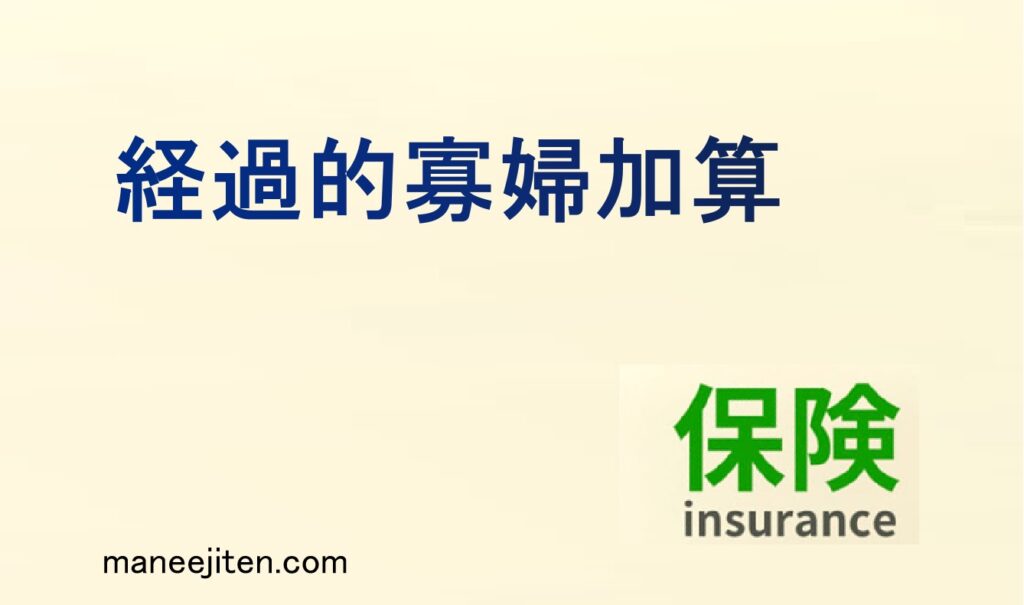年金を受け取るタイミングで、「あれ?65歳を過ぎたら年金額が減ってしまった?」と感じる方がいらっしゃいます。
とくに夫を亡くし、遺族厚生年金を受給している女性の中には、65歳以降に中高齢寡婦加算がなくなることで年金額が減少するケースがあるのです。
そこで登場するのが「経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)」という制度です。
本記事では、制度の背景や対象条件、支給額の仕組みまで、初心者にもわかりやすく解説します。
✅ 経過的寡婦加算とは?その目的と役割
「経過的寡婦加算」とは、65歳前後で急激に年金額が下がることを防ぐための加算制度です。
制度の背景:
-
夫を亡くした妻は、原則として遺族厚生年金を受け取ることができます。
-
さらに、40歳以上65歳未満で一定条件を満たすと「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。
-
しかし65歳になると、中高齢寡婦加算が終了し、自分自身の老齢基礎年金の受給が始まります。
このとき、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算より少ないと、結果的に年金総額が減ることになります。
その不公平を是正するために、導入されたのが「経過的寡婦加算」です。
📌 対象となるのは「1956年(昭和31年)3月31日以前」生まれの女性
経過的寡婦加算の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす方です:
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 生年月日 | 1956年(昭和31年)3月31日以前に生まれたこと |
| ② 遺族年金受給資格 | 遺族厚生年金を受給中であること |
| ③ 老齢基礎年金との関係 | 65歳以降に受給開始する老齢基礎年金の額が、中高齢寡婦加算より少ないこと |
この制度は、まさに“経過措置”としての位置づけで、今後対象者は徐々に減っていく見込みです。
💡 中高齢寡婦加算との違い
| 比較項目 | 中高齢寡婦加算 | 経過的寡婦加算 |
|---|---|---|
| 支給期間 | 40歳以上65歳未満 | 65歳以降 |
| 加算対象 | 遺族厚生年金に上乗せ | 遺族厚生年金に上乗せ |
| 目的 | 遺族年金だけでは生活が厳しい中高齢者を支援 | 65歳以降も年金額が急減しないよう補う |
| 支給条件 | 一定の婚姻期間等 | 1956年3月31日以前生まれ等の限定あり |
🧑🏫 支給のしくみ:いくら加算されるの?
経過的寡婦加算の金額は、「中高齢寡婦加算額と老齢基礎年金の差額」です。
たとえば:
-
中高齢寡婦加算額:約58,000円(月額)
-
自身の老齢基礎年金:52,000円(月額)
この場合、差額である6,000円が経過的寡婦加算として上乗せされます。
年金機構側が自動的に判定・計算して加算してくれますので、特別な手続きは不要です。
🚫 支給が止まるケースもある?障害年金との関係に注意
もしも対象者が「障害基礎年金の受給権」も持っている場合は、経過的寡婦加算は支給停止となります。
これは「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」は併給できないため、年金制度全体の整合性からこのような扱いになっています。
🌼 実際のシチュエーション:こんな方が対象です
ケース①:64歳まで中高齢寡婦加算を受けていた女性
65歳になり老齢基礎年金に切り替わったが、年金額が減ってしまう → 経過的寡婦加算で差額が補填される。
ケース②:ずっと専業主婦で、老齢基礎年金の額が少ない
夫の死後、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算で生活していた → 老齢基礎年金だけでは足りず、65歳以降も加算される。
🔍 よくある質問(FAQ)
Q. 経過的寡婦加算の申請は必要ですか?
➡ 原則として不要です。年金の裁定請求(老齢基礎年金の請求)をする際に、必要な情報が確認され、自動的に判断されます。
Q. いつまで支給されるの?
➡ 65歳以降、老齢基礎年金と中高齢寡婦加算との差額がある限り支給されます。
Q. 障害年金と重複できないのはなぜ?
➡ 日本の年金制度では、老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれか1つしか選択して受給できない制度設計となっているためです。
📝 まとめ:経過的寡婦加算は65歳以降の生活を支える重要な制度
経過的寡婦加算は、高齢期に年金額が急に下がるのを防ぐための“つなぎ”的な制度です。
対象となるのは限定的ですが、適用されれば生活の安定に大きく寄与します。
とくに「遺族厚生年金を受け取っていて、1956年3月31日以前生まれの方」は、65歳の年金受給切替時に自動的に対象となる可能性があるため、ご自身の年金額の変動に注意を払っておきましょう。
さらに参照してください: