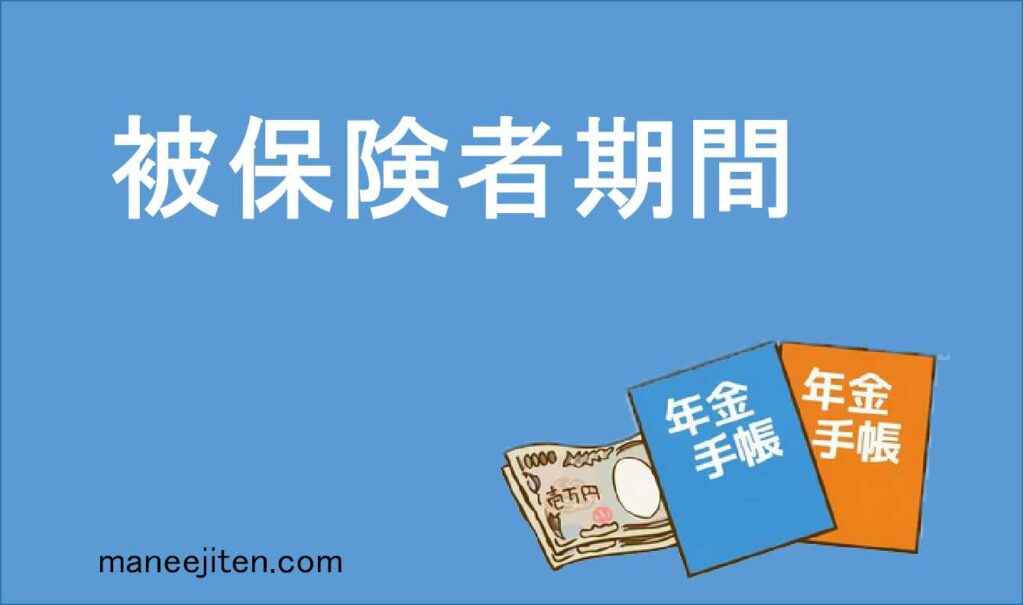年金の受給資格を考えるうえで、必ず登場する用語が 「被保険者期間(ひほけんしゃきかん)」 です。
「加入していた期間のことだろうな」とイメージはできても、実際には「免除期間は含まれるの?」「会社員を辞めた時はどうなるの?」と疑問に感じる方も多いはず。
この記事では、日本の年金制度における被保険者期間を、初心者にもわかりやすく解説します。年金をしっかり受け取るために、ぜひ理解しておきましょう。
被保険者期間とは?
被保険者期間とは、国民年金や厚生年金保険に加入していた期間 のことをいいます。
計算は「その月の初日から末日まで加入していたかどうか」で行われ、被保険者となった月から資格を失った前月まで を月単位で数えます。
例えば、
-
2020年4月に会社へ入社し厚生年金に加入 → 被保険者期間は2020年4月からスタート
-
2023年3月に退職して厚生年金の資格を喪失 → 被保険者期間は2023年2月まで
このように「資格を失った月の前月まで」がカウントされるのがポイントです。
老齢基礎年金と被保険者期間の関係
年金を受け取るには、原則 10年以上の被保険者期間 が必要です。
そして、この「被保険者期間」には、実際に保険料を納めた月だけでなく、次のような期間も含まれます。
1. 保険料を納めた期間
-
自営業などで国民年金保険料を支払った期間
-
会社員・公務員として厚生年金に加入していた期間
2. 保険料免除期間
-
所得が少ない場合などに申請して認められた免除期間
-
全額免除・一部免除ともに対象
3. 合算対象期間(カラ期間)
-
学生時代に国民年金に任意加入していなかった期間(昭和36年4月以降)
-
海外に住んでいた期間(20歳以上65歳未満で日本の年金制度に加入していなかった場合)
合算対象期間は年金額には反映されませんが、「受給資格期間」には含めることができます。
具体例:こんな人の被保険者期間はどうなる?
-
会社員を10年 → 自営業で5年 → 免除期間3年
→ 合計18年の被保険者期間(受給資格クリア) -
学生時代に未加入5年 → 会社員で7年 → 全額免除2年
→ 実際に保険料を納めたのは7年だが、免除2年と未加入の合算対象5年を足して 受給資格期間は14年
このように「保険料を払った期間」だけでなく、免除やカラ期間も重要な役割を果たします。
被保険者期間を確認する方法
「自分の被保険者期間がどのくらいあるか」を調べたい場合は、以下の方法が便利です。
-
ねんきん定期便:毎年誕生日月に送付される通知で確認可能
-
ねんきんネット:日本年金機構のウェブサービス。加入記録を24時間確認できる
-
年金事務所:窓口で「年金加入記録」を請求できる
まとめ
被保険者期間は、年金の受給資格を判断するうえで欠かせない概念です。
-
国民年金や厚生年金に加入していた月単位の期間
-
納付期間だけでなく「免除期間」や「合算対象期間」も含まれる
-
老齢基礎年金の受給には10年以上の被保険者期間が必要
「自分はまだ年金は先の話」と思っていても、加入や免除の手続き次第で将来の受給額や受給資格に影響します。
早めに自身の記録を確認し、不安があれば年金事務所に相談することをおすすめします。
さらに参照してください: