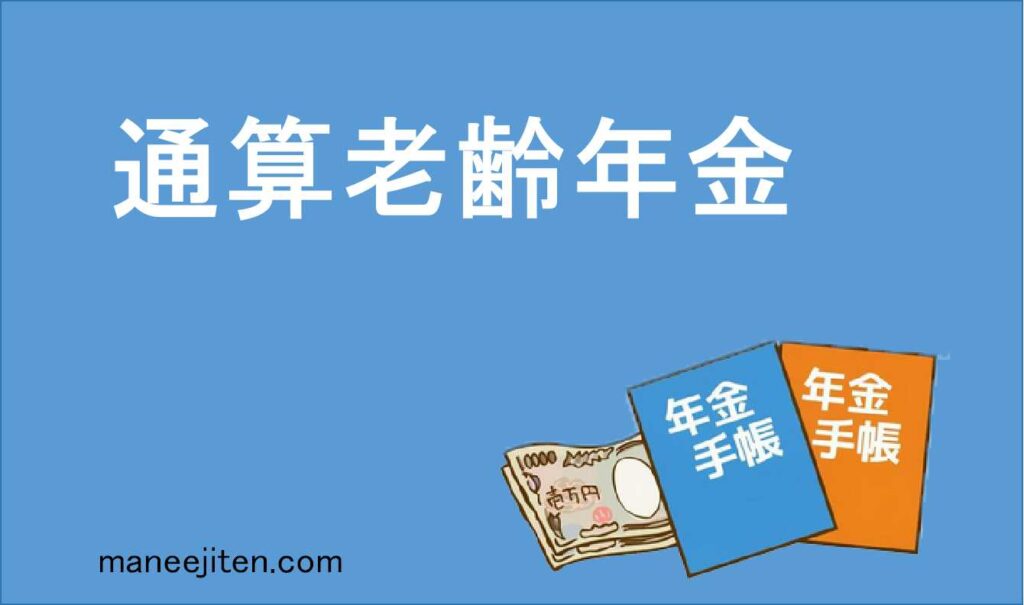かつて日本の年金制度には「通算老齢年金」という仕組みがありました。
これは、複数の年金制度に加入していたものの、それぞれの制度で受給資格を満たせない人を救済するための年金です。
現在は廃止されていますが、その背景を知ることで、日本の年金制度の仕組みや進化をより理解できるようになります。
通算老齢年金とは?
通算老齢年金(つうさんろうれいねんきん)とは、1926年(大正15年)4月1日以前生まれの人を対象に設けられた特別な年金制度です。
制度のポイント
-
対象:複数の年金制度(例:厚生年金、共済年金など)に加入していた人
-
条件:それぞれの制度で「老齢年金の受給資格期間」を満たさない場合
-
内容:複数の制度の加入期間を「通算」し、合算した期間で受給資格を満たした場合に支給
つまり、各制度に1年以上加入していても「単独では資格不足」の人が、通算することで年金を受け取れるようにする救済的な制度でした。
なぜ通算老齢年金が必要だったのか?
昔の年金制度は、制度ごとに加入期間を別々に計算していました。
たとえば:
-
厚生年金に8年加入
-
共済年金に7年加入
この場合、どちらの制度も「最低10年の加入要件」を満たさないため、どちらからも年金がもらえない問題がありました。
そこで、「通算老齢年金」が導入され、8年+7年=15年として資格を満たせるようにし、各制度の加入期間に応じた年金額が支給されたのです。
廃止された理由
通算老齢年金は1986年(昭和61年)4月の基礎年金制度の導入によって廃止されました。
基礎年金導入後は、どの年金制度に加入してもすべて国民年金の「老齢基礎年金」の受給資格期間に算入されるようになったため、通算という仕組み自体が不要になったのです。
現在の制度との違い
-
昔(通算老齢年金あり)
-
各制度で資格を満たせない人を救済
-
制度ごとの加入期間を合算して年金受給が可能
-
-
現在(基礎年金制度導入後)
-
どの制度に加入しても国民年金に合算
-
「受給資格期間=10年」で一元化
-
通算の仕組みは不要
-
まとめ
通算老齢年金は、複数の制度に加入していたのに年金をもらえない人を救済するための過去の制度です。
1986年の基礎年金制度の導入により、加入期間が一元化され、現在では通算老齢年金は存在しません。
現在は、どの年金制度に加入してもすべて「老齢基礎年金」の資格期間にカウントされるため、より分かりやすく、公平な仕組みに整備されています。
さらに参照してください: