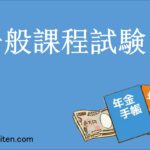「逸失利益」という言葉は、交通事故の賠償や保険の説明などで耳にすることがある用語です。
でも「難しそうでよくわからない」という方も多いでしょう。
この記事では、逸失利益の意味、計算の考え方、具体例を交えて、初心者にもわかりやすく解説します。
✅ 逸失利益とは?基本の意味
**逸失利益(いっしつりえき)**とは、
本来であれば将来得られたはずの利益が、不法行為(例:交通事故)や債務不履行などによって失われてしまったもの
を指します。
特に交通事故の損害賠償請求の場面で重要な用語です。
✅ 交通事故における逸失利益のイメージ
わかりやすく例を挙げます。
例えば:
-
被害者が交通事故で死亡してしまった
-
本来であれば、65歳まで働いて給料を得られた
この「将来得られるはずだった給料(収入)」が逸失利益です。
つまり、
事故がなければ得られた金銭的利益を、加害者側が賠償する
という考え方です。
✅ 逸失利益の具体例
例えば30歳の会社員が交通事故で亡くなった場合。
-
本来は65歳まで35年間働けた
-
年収500万円を得られた可能性がある
とすると、将来得られる総収入(500万円 × 35年)がベースになります。
ただし、そのまま全額を賠償するのではなく、実際の計算では以下を考慮します。
✅ 生活費の控除
被害者が生きていれば、自分の生活費を使ったはずなので、その分を引く。
✅ 中間利息控除(現価計算)
将来分をまとめて今払うので、利息を考慮して割り引く。
✅ 逸失利益の計算方法(基本の考え方)
一般的な計算式(死亡事故の場合の例):
逸失利益 = (基礎収入 - 生活費控除分) × 就労可能年数分のライプニッツ係数
-
基礎収入:事故がなければ得たと予想される年収
-
生活費控除率:一般的に30〜50%程度(被扶養者の有無で変わる)
-
ライプニッツ係数:中間利息を考慮し、将来収入を現在価値に換算する係数
実際の計算はケースごとに異なるため、専門家や弁護士に相談するのが一般的です。
✅ 後遺障害が残った場合の逸失利益
交通事故で死亡しなくても、重い後遺障害が残った場合にも逸失利益は発生します。
例えば:
-
事故の後、労働能力が50%失われた
-
その分、将来得られるはずの収入が減少した
この「労働能力喪失分」も逸失利益として加害者に請求できます。
✅ 逸失利益と保険金
自動車保険(任意保険・自賠責保険)では、被害者が加害者に請求する賠償金に含まれる形で逸失利益がカバーされます。
-
加害者側の保険会社が支払う賠償金の中に、逸失利益分も含む
-
ただし保険金額の上限や過失割合などにより、全額賠償されるとは限らない
✅ まとめ
逸失利益とは、交通事故などの不法行為がなければ将来得られたはずの利益を、加害者が賠償するものです。
✅ 交通事故では
-
死亡 → 就労可能年数分の収入をもとに算定
-
後遺障害 → 労働能力喪失分を計算
専門的な計算が必要な部分も多いですが、**「将来失った収入を補償する」**という基本の考え方を押さえることが大切です。
さらに参照してください: