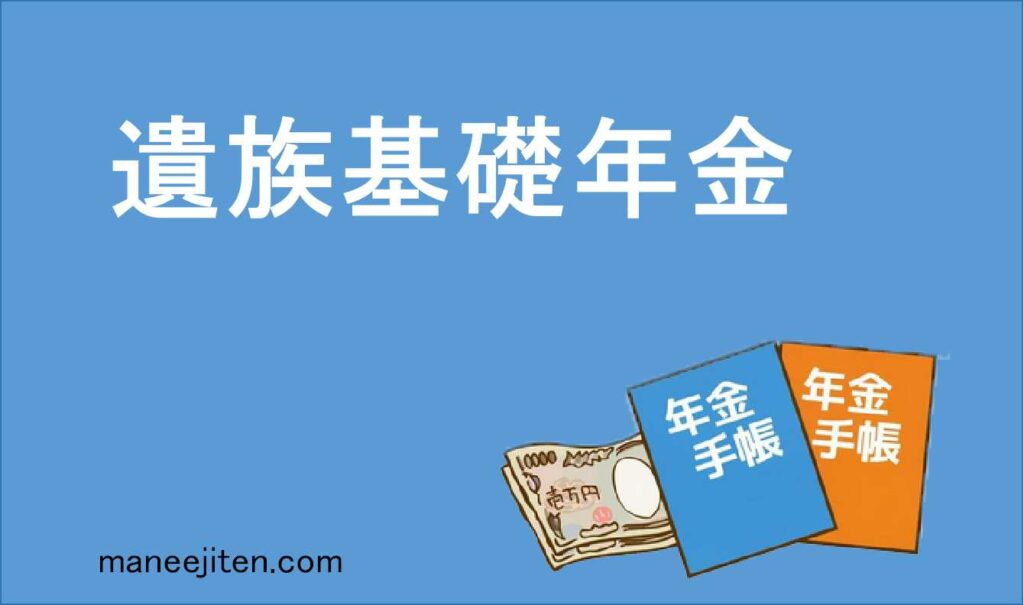子育て中の家庭にとって、万が一の備えはとても大切です。
その中でも「遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)」は、国民年金制度の中で家族を支える重要な給付のひとつです。
この記事では、遺族基礎年金の仕組みや受給できる条件、注意すべきポイントを初心者にもわかりやすく解説します。
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金とは、国民年金に加入している人や、一定の条件を満たす人が亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。
遺族に対して経済的な支えを提供することで、生活の安定を図ることを目的としています。
遺族基礎年金を受け取れる遺族
遺族基礎年金を受けられるのは、次のいずれかにあたる人です。
-
子のある配偶者
-
子(18歳の年度末まで、または20歳未満で1級・2級の障害がある未婚の子)
ただし、子が死亡した人の配偶者に生計を維持されている場合、その子に対する遺族基礎年金は支給停止となります。
支給の対象となる被保険者
遺族基礎年金の支給対象となるのは、次のいずれかの人が死亡した場合です。
-
国民年金に加入中の人
-
国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
-
受給資格期間が25年以上ある人
-
老齢基礎年金と異なり、10年ではなく25年以上の資格期間が必要となります。
-
保険料納付に関する条件
さらに、次の保険料納付要件を満たす必要があります。
-
加入期間のうち 3分の1以上の期間で保険料を滞納していないこと
-
または 直近1年間に保険料の滞納がないこと(令和8年4月前の死亡の場合)
これを満たしていないと、遺族基礎年金は受け取れませんので注意が必要です。
具体例で理解する遺族基礎年金
例えば、国民年金に加入している30代の夫が不慮の事故で亡くなり、妻と小学生の子どもが残された場合、妻が「子のある配偶者」として遺族基礎年金を受け取ることができます。
子どもが18歳の年度末を迎えると、受給資格が終了するため、その後の生活設計を考える必要があります。
まとめ
遺族基礎年金は、子どもを養育する家庭にとって大切な生活保障です。
ただし、受給には「対象者の範囲」「保険料納付要件」「資格期間」などの条件があるため、正しく理解しておくことが重要です。
もしもの時に遺族が安心して生活できるように、日ごろから年金制度を理解し、保険料の納付を確実にしておくことが、最大の備えとなります。
さらに参照してください: