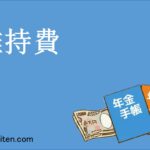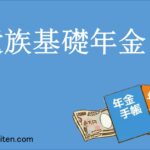「遺贈」という言葉を聞いたことはあっても、「相続とどう違うの?」「どんな仕組み?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺贈の意味や種類、相続との違い、具体的な注意点を初心者向けにやさしく解説します。
✅ 遺贈(いぞう)とは?
遺贈とは、遺言によって自分の財産を他者や団体に無償で譲ることをいいます。
生前に「自分が亡くなったら、この財産をこの人にあげたい」と決め、それを遺言書に残すことで実現する仕組みです。
たとえば、家族以外の友人や特定の団体、公益法人、学校、自治体などに財産を贈ることもできます。
🌟 具体例
-
「私が亡くなったら、この別荘を長年の友人Aさんに遺贈する」
-
「遺産の10%を〇〇市に寄付する」
✅ 遺贈の種類
遺贈には大きく分けて次の2つの形があります。
✅ ① 特定遺贈
-
特定の財産を指定して渡す
-
例:「自宅の土地建物をAさんに渡す」「預金口座の500万円をBさんに贈る」
➡️ 何を誰にあげるかを明確に指定するので、受け取る人も内容もはっきりします。
✅ ② 包括遺贈
-
財産全体や一定割合をまとめて渡す
-
例:「全財産をCさんに遺贈する」「遺産の半分をDさんに渡す」
➡️ 財産の範囲を網羅的に指定する形で、相続分と似たイメージになります。
包括遺贈を受けた人は、相続人と同じように債務も承継する場合があるため注意が必要です。
✅ 遺贈と相続の違い
| 項目 | 遺贈 | 相続 |
|---|---|---|
| 基本 | 遺言による | 法律上の規定に基づく |
| 受取人 | 相続人以外も指定可能 | 法定相続人に限る(ただし遺言で指定も可) |
| 承継の範囲 | 特定の財産または包括的に指定 | 全財産を承継 |
✅ 遺贈は、相続人以外の人や団体に遺産を渡す手段として特に活用されます。
✅ 遺贈の注意点
-
遺留分に注意
相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。
たとえば「全財産を第三者に遺贈する」と書いても、相続人が遺留分を請求すれば一部は取り戻される可能性があります。 -
遺言書の形式要件
遺贈を有効にするには、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
公正証書遺言や自筆証書遺言などの方式を守りましょう。 -
受遺者が拒否することも可能
受け取る人(受遺者)が「受け取らない」と放棄することも可能です。
✅ 遺贈はどんなときに使う?
✅ 子どもがいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい
✅ 相続人以外の人(友人や介護をしてくれた人など)にお礼をしたい
✅ 社会貢献のために団体や自治体に寄付したい
遺贈は自分の意思を反映しやすい方法として、相続対策でもよく使われます。
✅ まとめ
「遺贈(いぞう)」とは、遺言で財産を他者や団体に無償で譲る仕組みです。
✅ 特定の財産を渡す「特定遺贈」
✅ 全体や割合を指定する「包括遺贈」
✅ 相続人以外にも自由に指定可能
自分の財産をどう分けたいかを考える際に、遺贈は大切な選択肢のひとつです。
ただし、遺留分などの制約もあるため、専門家に相談しながら計画することをおすすめします。
さらに参照してください: