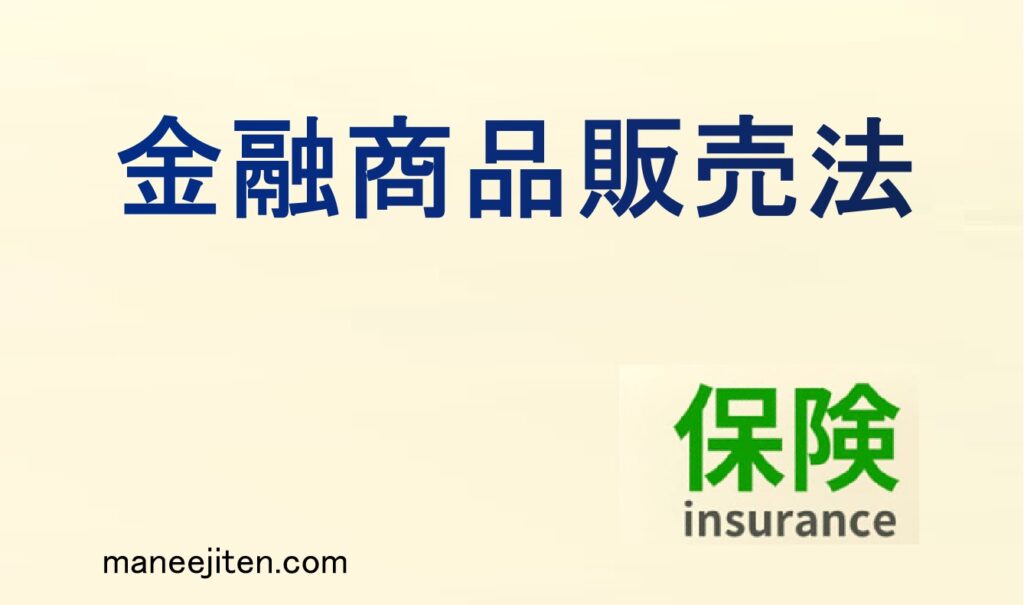**「金融商品販売法(きんゆうしょうひんはんばいほう)」**は、預貯金・保険・株式など、私たちの生活に身近な「金融商品」を安心して購入できるようにするためのルールを定めた法律です。
この法律は、2001年に施行され、2020年に**「金融サービス提供法」**へと統合・改称されました。
本記事では、法律の内容や背景、具体的な事例を交えて、初心者にもわかりやすく解説します。
金融商品販売法とは?その目的と背景
◼ 安心して「金融商品」を選ぶための法律
金融商品販売法は、金融機関が金融商品を販売する際に守るべきルールを定めた法律です。
主な目的は、
-
消費者(契約者)の保護
-
金融機関による過剰な勧誘や誤解を招く説明の防止
-
トラブルの未然防止
といった点にあります。
具体的にどんなルールがある?
1. 重要事項の説明義務
金融機関は、保険商品や投資信託などを販売する際に、以下のような重要な情報を事前に説明する義務があります。
-
元本割れのリスク
-
手数料や契約期間
-
解約時の返戻金や制限事項
例:
終身保険を販売する際、「途中解約すると元本割れのリスクがある」と説明しなければなりません。
2. 断定的判断の提供の禁止
「この商品は絶対に儲かります!」というような断定的な言い方は禁止されています。
将来の運用成果は誰にもわからないため、事実に基づかない勧誘は法律違反とされます。
例:
「10年後には確実に増えます」といったセールストークはアウトです。
2020年に「金融サービス提供法」へ
◼ 法律が変わった理由
多様化する金融サービスに対応するため、金融商品販売法は2020年に改正され、「金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)」として生まれ変わりました。
これは2021年に施行されています。
改正によって、
-
金融商品販売業者の登録制度の整備
-
金融ADR(裁判外紛争解決制度)の一本化
などが強化され、消費者の利便性と保護がより高まりました。
この法律が関係してくるシチュエーション
✅ 保険の契約をするとき
たとえば生命保険に加入する際、「告知義務」や「保険金の支払条件」について説明を受けた経験はありませんか?
それは、この法律に基づいた重要事項の説明義務にあたります。
✅ 銀行や証券会社で投資商品をすすめられたとき
「この投資信託はリスクがあります」と言われたのは、断定的な勧誘を避けるための対応です。
まとめ|金融商品販売法は「消費者を守る」ための基本ルール
金融商品販売法は、保険や預金、株式といった私たちの大切なお金に関わる商品を安心して選べるように整備されたルールです。
現在は「金融サービス提供法」として、より広範な分野をカバーしていますが、基本的な考え方──「重要なことはきちんと説明する」「誤解を招く表現は使わない」──は変わっていません。
これから保険に加入したり、投資を始めたりする方は、ぜひこの法律の存在を知っておきましょう。
さらに参照してください: