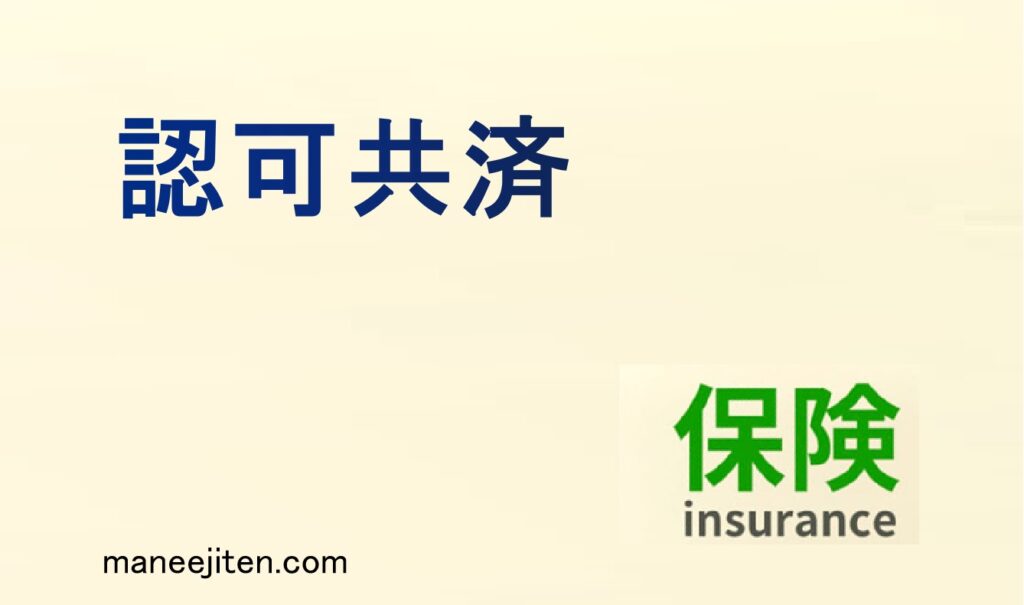共済という言葉は耳にしたことがあっても、「認可共済」と「無認可共済」の違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
実はこの違いは、契約者の安心度や保護の手厚さに直結する大切なポイントです。
この記事では、「認可共済」の基本的な仕組みや代表的な例、さらに「無認可共済」との違いについて、初心者にもわかりやすく解説します。
認可共済とは?
認可共済(にんかきょうさい)とは、法律に基づいて設立され、金融庁や農林水産省などの監督官庁から認可を受けて運営されている共済のことをいいます。
特徴としては:
-
財務状況の公表義務がある
-
監督官庁のチェックを受けている
-
契約者保護のルールが整っている
つまり、認可共済は公的な規制のもとで運営されており、安心して利用できる仕組みが整っています。
認可共済の代表例
日本で代表的な認可共済には次のようなものがあります。
-
JA共済(農協が運営する共済)
-
全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)
-
CO-OP共済(生活協同組合が運営)
いずれも大規模な組織が運営しており、生命保険や自動車保険、火災保険に相当するような保障商品を取り扱っています。
無認可共済との違い
一方で、かつては「無認可共済」と呼ばれる共済も数多く存在していました。
-
無認可共済:保険業法や特別な法律に基づかず、監督官庁が存在しない共済
-
法律上のチェックがないため、マルチ商法的な勧誘や契約トラブルが多発していた
このような背景から、2006年(平成18年)4月の「保険業法等の一部を改正する法律」によって、根拠法のない共済も契約者保護ルールの対象となりました。
その結果、無認可共済は:
-
保険会社
-
少額短期保険業者
のいずれかに移行することが義務化され、契約者保護の枠組みが整えられました。
認可共済に加入するメリット
認可共済に加入する最大のメリットは、安心感です。
-
監督官庁によるチェックがあるため、財務基盤の健全性が保たれている
-
万一のトラブル時にも契約者保護ルールが整っている
-
大規模な組織が運営しており、利用者も多い
例えば、「万が一の医療費に備えたい」「自動車事故の保障を準備したい」といった場合、認可共済の商品は一般の保険会社の商品と同じように選択肢になり得ます。
まとめ
認可共済とは、法律に基づいて設立され、監督官庁から認可を受けた安心できる共済制度のことです。
-
JA共済、全労済、CO-OP共済などが代表例
-
無認可共済との違いは「法的な規制と監督の有無」
-
2006年の法改正以降、無認可共済は保険会社などへの移行が義務化
「保険と共済の違いがよくわからない」「安心できるのはどちら?」と悩む方は、まず認可共済かどうかを確認するとよいでしょう。
さらに参照してください: