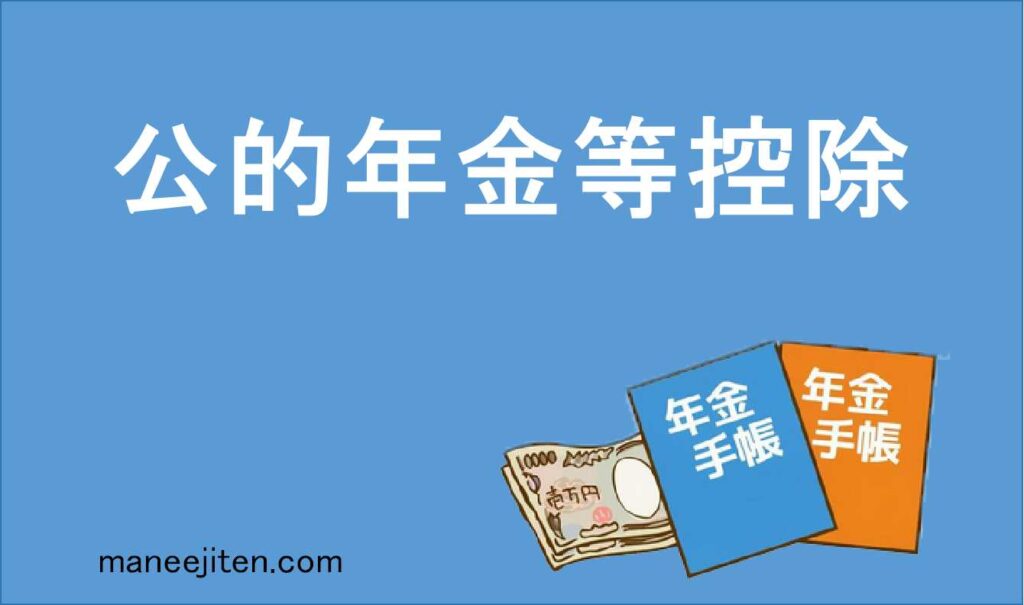年金を受け取るようになると「税金ってかかるの?」と不安に思う方は少なくありません。
実際、老齢年金は所得税の対象となりますが、そのまま全額に税金がかかるわけではありません。
ここで重要になるのが「公的年金等控除」です。
これは会社員の給与所得控除にあたるもので、年金受給者の税負担を軽くする仕組みです。
本記事では、公的年金等控除の基本から控除額の違い、計算の流れまで、初心者にもわかりやすく解説します。
公的年金等控除とは?
公的年金等控除とは、年金収入がある人に適用される所得控除の一種です。会社員にとっての「給与所得控除」と同じ役割を持ち、年金収入から一定の金額を差し引くことで課税対象を少なくします。
対象となる年金は以下の通りです:
-
老齢基礎年金・老齢厚生年金
-
厚生年金基金
-
確定給付企業年金
-
確定拠出年金(年金として受け取る場合)
これらはすべて「雑所得」として扱われ、まず公的年金等控除を差し引いたうえで、さらに配偶者控除や扶養控除などを適用した残りの所得に対して課税されます。
控除額は年齢によって異なる
公的年金等控除は、受給者の年齢によって控除額が変わります。
65歳未満の場合
65歳未満の人が受給する年金については、一定額の控除が設けられています。年金収入が少ない場合は、控除によってほぼ課税されないケースもあります。
65歳以上の場合
65歳以上では控除額が大きく設定されており、年金生活者の負担がさらに軽くなります。特に、一定額以下の年金収入であれば所得税がかからないことも多いのです。
公的年金等控除の計算イメージ
例えば、65歳以上で年間の年金収入が 200万円 の場合を考えてみましょう。
-
年金収入200万円から「公的年金等控除」を差し引く
-
さらに基礎控除や配偶者控除などが適用される
-
残った金額が課税対象となる
この仕組みにより、年金生活者の多くが実際には少額、あるいは非課税となります。
まとめ
公的年金等控除とは、年金受給者にとっての「税負担を軽くする仕組み」であり、会社員の給与所得控除に相当します。65歳未満と65歳以上で控除額が異なり、多くのケースで控除によって課税額が大きく抑えられるのが特徴です。
年金を受け取り始めたとき、「思ったより税金がかからない」と感じる方が多いのは、この控除があるからです。年金生活を安心して送るためにも、公的年金等控除の仕組みを正しく理解しておきましょう。
さらに参照してください: