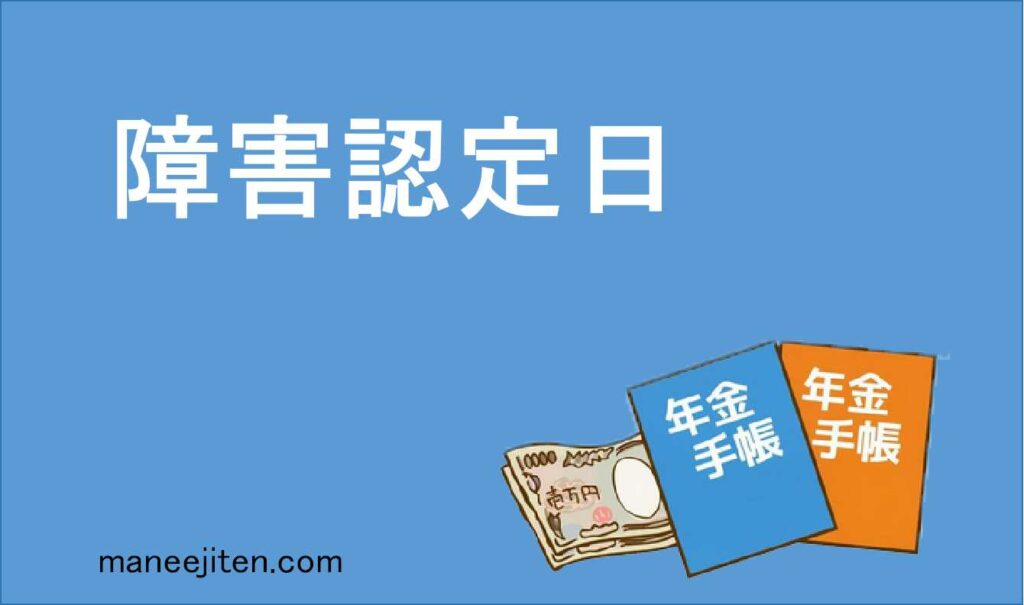障害年金を請求するうえで重要になるのが「障害認定日」です。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、年金の受給可否や等級の判断に直結する大切な基準日です。
本記事では、障害認定日の基本的な仕組みや具体例、注意点をわかりやすく解説します。
障害認定日とは?
「障害認定日」とは、障害の状態を定める基準日を指します。原則として 病気やけがの初診日から1年6か月を経過した日 が障害認定日になります。
ただし、1年6か月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)は、その治った日が障害認定日となります。
特例としての障害認定日
一部の病気や治療については、1年6か月を待たずに障害認定日が設定されます。代表的なケースは以下の通りです。
-
人工透析療法:透析開始から3か月経過した日
-
人工関節や人工骨頭のそう入置換:そう入置換を行った日
-
心臓ペースメーカーや人工弁の装着:装着した日
-
人工肛門の造設や尿路変更術:手術から6か月経過した日
-
新膀胱を造設:造設した日
-
切断・離断による障害:切断・離断の日(障害手当金の場合は創面治癒日)
-
喉頭全摘出:全摘出を行った日
-
在宅酸素療法:開始した日
障害認定日が重要な理由
障害認定日は、障害年金の受給可否や等級を判断する基準になります。
この日の状態をもとに「障害等級(1級~3級)」が決定されるため、診断書の内容や日付が非常に重要です。
申請時の注意点
-
診断書の記載日と障害認定日が一致しているか確認しましょう。
-
認定日の状態で受給要件を満たさない場合でも、その後に状態が悪化した場合は「事後重症請求」という制度で申請可能です。
-
初診日の証明が困難なケースもあるため、受診記録や紹介状を大切に保管しておきましょう。
まとめ
障害認定日は、障害年金の受給において欠かせない基準日です。原則は「初診日から1年6か月後」ですが、人工透析や人工関節など一部のケースでは例外が設けられています。申請にあたっては、医師の診断書や受診記録をしっかり確認し、必要に応じて年金事務所や専門家に相談することをおすすめします。
さらに参照してください: