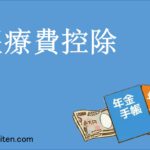「遺言で全部あげないと言われたら、相続できないの?」
「遺留分ってどういう制度?」
相続の話題でよく出てくる「遺留分(いりゅうぶん)」。
これは、被相続人(亡くなった方)が自由にできる遺産の分配に一定の制限をかけ、相続人の最低限の取り分を保障する仕組みです。
ここでは、遺留分の意味や対象者、割合、請求の流れまで、初心者でもわかるようにやさしく解説します。
✅ 遺留分とは?基本の意味
**遺留分(いりゅうぶん)**とは、
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が、法律上必ずもらえる最低限の相続分
のことをいいます。
✅ 民法第1028条に規定
✅ 被相続人が全財産を特定の人に遺贈する遺言を書いても、遺留分の権利は奪えません
✅ なぜ「遺留分」があるの?
遺留分は、相続人の生活保障や公平を守るための制度です。
✅ 被相続人の「財産処分の自由」と
✅ 相続人の「生活権・公平」
このバランスを取るために、法律で最低限の取り分を保障しています。
✅ 遺留分が認められる人は?
「誰でも遺留分を請求できるわけではない」点が重要です。
✅ 遺留分権利者
-
配偶者
-
子(代襲相続人含む)
-
直系尊属(父母・祖父母など)
✅ 被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない
→ 兄弟姉妹は法定相続人でも、遺留分を請求する権利はありません。
✅ 遺留分の割合は?
遺留分の割合は法律で決まっています。
✅ 相続財産の 1/2(直系尊属のみが相続人の場合は 1/3)が「遺留分の基礎」
そこから各相続人の法定相続分に応じて計算します。
● 例1:配偶者と子が相続人
-
法定相続分:配偶者1/2、子1/2
-
遺留分の基礎:相続財産の1/2
-
→ 配偶者の遺留分:1/4、子の遺留分:1/4
● 例2:親だけが相続人
-
遺留分の基礎:相続財産の1/3
-
親2人の場合、それぞれ1/6ずつ
✅ このように、相続人の構成で具体的な割合が変わります。
✅ 遺留分を侵害されたら?「遺留分侵害額請求」
「全部を第三者に贈与する」という遺言があっても、遺留分権利者は黙っている必要はありません。
✅ 遺留分を侵害された場合は
→ **遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)**ができます。
● 請求方法のイメージ
-
内容証明郵便などで侵害者に請求を通知
-
話し合い(交渉)で解決
-
解決しない場合は調停・訴訟へ
✅ 金銭で請求するのが原則
2020年の民法改正で、物権的返還請求から金銭請求が基本に変わりました。
✅ よくある質問(FAQ)
Q. 遺留分はいつまでに請求するの?
-
時効は原則1年
→ 相続開始と侵害を知ったときから1年以内 -
長くても相続開始から10年で消滅
Q. 遺留分放棄はできる?
-
生前でも可能ですが、家庭裁判所の許可が必要
✅ まとめ
**遺留分(いりゅうぶん)**は、
相続人の最低限の取り分を保障する法律上の制度。
✅ 被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる
✅ 配偶者・子・直系尊属が対象
✅ 遺言で全財産を他人に渡す指定をしても、遺留分は守られる
✅ 侵害されたら「遺留分侵害額請求」で金銭を請求可能
相続対策を考えるときは、遺言を書く側も受ける側も、この遺留分を正しく理解することが大切です。
さらに参照してください: