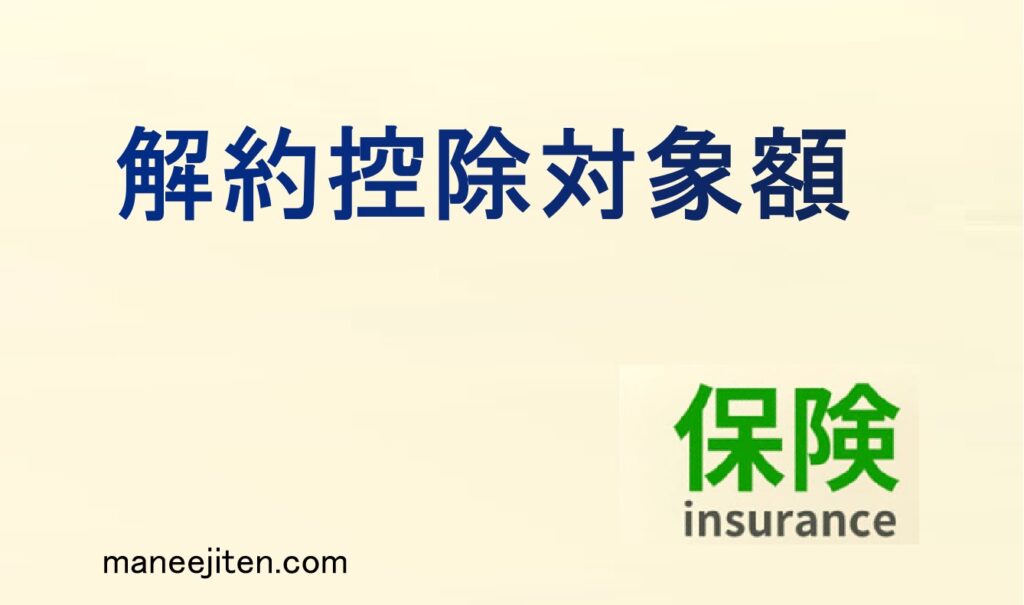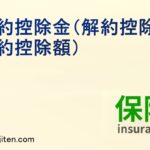「保険を解約したらお金が返ってくると思ったのに、全然戻らない…」
そんな声の理由のひとつが「解約控除」の仕組みです。
この記事では、特にその計算の元になる 解約控除対象額(かいやくこうじょたいしょうがく) について、初心者にもわかりやすく解説します。
✅ 解約控除対象額とは?
解約控除対象額とは、保険を途中解約する際に「解約控除金(解約控除額)」を計算するための基準になる金額のことです。
もっと簡単に言うと:
「解約時の手数料を計算するための元となるお金の部分」
です。
✅ そもそも解約控除とは?
保険を短期間で解約したとき、保険会社は販売・事務コストを回収できないリスクを抱えます。
そのため、解約返戻金から「解約控除金」という手数料的なお金を差し引きます。
-
解約控除金(解約控除額)= 解約控除対象額 × 解約控除率
-
つまり「控除対象額」がなければ控除金も計算できない
✅ 解約返戻金との関係
解約返戻金は保険を解約したときに契約者に戻るお金です。
ただし、その金額は単純ではありません。
一般的な計算イメージ:
-
責任準備金:保険会社が将来の保険金支払いのために積み立てたお金
-
解約控除金:短期解約の際に差し引く手数料的なもの
-
解約控除対象額:その控除金を計算するための基準
▶️ 【具体例イメージ】
例えば…
✅ 加入から2年目で解約
✅ 責任準備金:50万円
✅ 解約控除対象額:45万円
✅ 解約控除率:10%
計算は以下のようになります。
短期解約だと解約控除率が高めに設定され、戻るお金が大きく減ることがあります。
✅ なぜ解約控除対象額があるの?
保険は長期契約を前提に成り立つ仕組みです。
初期の営業・設計・事務コストを回収する前に解約されると保険会社は赤字になります。
✅ この負担を公平に調整するため
✅ 途中解約時には責任準備金から控除を引く仕組み
これが「解約控除」ですが、その控除金を計算するために設定されているのが「解約控除対象額」です。
✅ 解約返戻金が増えるタイミングは?
-
保険料を長く払い込むほど、責任準備金が増える
-
解約控除率も年数経過で下がる、またはゼロになる
-
10年以上払い込むと解約控除がなくなる商品設計も多い
つまり、長期契約を続けるほど返戻率は高くなるのが一般的です。
✅ 解約を検討するときのポイント
✅ 解約控除対象額や控除率を必ず確認する
✅ 早期解約だと返戻金が大きく減ることを理解する
✅ 減額や払い済みなど解約以外の選択肢も検討する
✅ まとめ
✅ 解約控除対象額とは:解約控除金を計算する基準となる金額
✅ 解約返戻金の計算式:責任準備金 − 解約控除金
✅ 短期解約は損失大:控除金が多く引かれる
保険は長期の安心を買う仕組みです。
解約を考える際は、解約控除対象額や解約返戻金の仕組みを理解し、計画的に判断しましょう。
さらに参照してください: