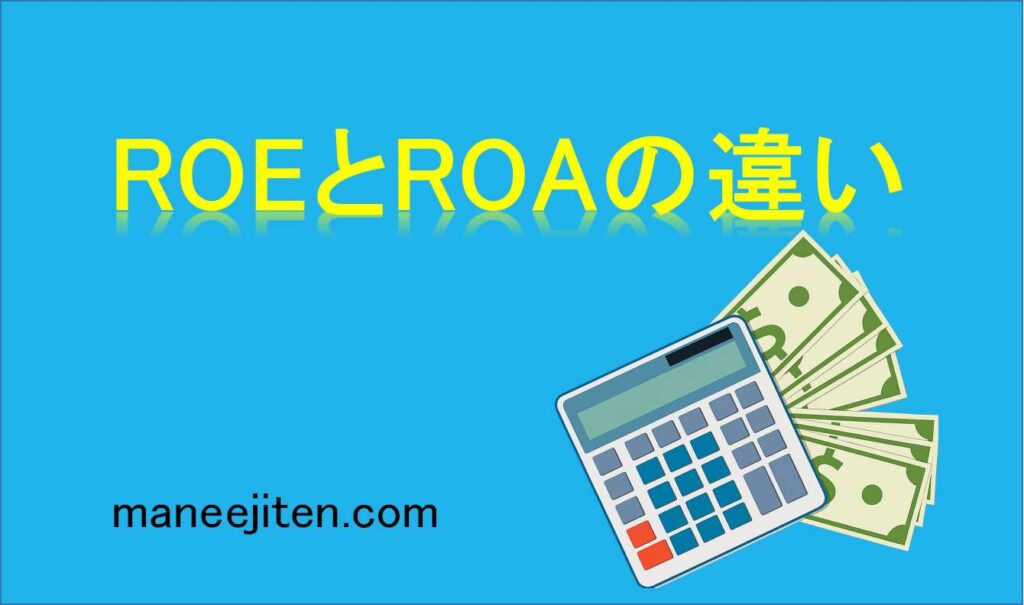企業の収益性を評価する際によく登場する指標に「ROE」と「ROA」があります。
どちらも利益の効率性を示す重要な指標ですが、計算式や意味は異なります。
この記事では、ROEとROAの基本的な違い、計算方法、目安、そして経営分析への活かし方をわかりやすく解説します。
ROEとは?自己資本利益率の意味
ROE(Return On Equity)は「自己資本利益率」と呼ばれ、自己資本に対してどれだけの利益を上げているかを示す指標です。
自己資本とは返済の必要がない資金のことで、株主からの出資金や過去の利益の蓄積(内部留保)などを指します。
ROEが高い企業ほど、株主から預かった資金を効率的に運用して利益を上げていると判断できます。
ROEの計算式
ROE(%)= 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
【例】
A社:当期純利益 1,000万円、自己資本 1億円
B社:当期純利益 1,500万円、自己資本 1億円
A社:1,000万円 ÷ 1億円 × 100 = 10%
B社:1,500万円 ÷ 1億円 × 100 = 15%
この場合、B社の方が自己資本をより効率的に活用して利益を生み出しているといえます。
ROEの目安
一般的に、ROEが8~10%以上あれば「優良企業」と判断されることが多いです。
ただし、業種によって平均値が異なります。製造業では約9%前後、情報通信業では12%前後が平均的な水準とされています。
ROEは投資家にとって企業の「資本効率」を測る重要な指標であり、投資判断の材料として広く利用されています。
ROEを改善する方法
ROEを高めるには、次の2つの方向からアプローチできます。
-
当期純利益を増やす(売上向上やコスト削減で収益性を改善)
-
自己資本を減らす(不要な資産や在庫を処分し、資本を効率化)
ただし、無理に自己資本を減らすと財務体質が悪化する可能性もあるため、バランスが重要です。
ROAとは?総資産利益率の意味
ROA(Return On Assets)は「総資産利益率」と呼ばれ、会社が保有する全資産に対してどれだけの利益を上げているかを示します。
現金、売掛金、設備、土地などの総資産をどれだけ効率的に活用できているかを表すため、経営全体の効率を見る際に用いられます。
ROAは投資家だけでなく、取引先や金融機関も注目する指標です。
ROAの計算式
ROA(%)= 当期純利益 ÷ 総資産 × 100
【例】
A社:当期純利益 1,000万円、総資産 2億円
B社:当期純利益 1,500万円、総資産 5億円
A社:1,000万円 ÷ 2億円 × 100 = 5%
B社:1,500万円 ÷ 5億円 × 100 = 3%
この場合、B社の方が利益額は大きいものの、資産効率の面ではA社の方が優れています。
ROAの目安
ROAは一般的に 5%前後 が一つの基準とされます。
ただし、業種によって資産構成が大きく異なるため、同業他社と比較することが大切です。
製造業は5%前後、情報通信業は6%前後、サービス業は3~4%程度が目安とされています。
ROAを改善する方法
ROAを向上させるには、次の2つのアプローチが有効です。
-
当期純利益を増やす(売上アップ、コスト削減など)
-
総資産を減らす(在庫・固定資産の見直し、投資の整理など)
特に、使われていない設備や過剰在庫の削減は、資産効率を高める効果があります。
ROEとROAの違い
| 指標 | 計算式 | 分母 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| ROE | 当期純利益 ÷ 自己資本 | 自己資本(株主資本) | 株主資本の収益性を測る |
| ROA | 当期純利益 ÷ 総資産 | 総資産(負債+資本) | 資産全体の効率を測る |
ROEは「株主が出資した資金に対してどれだけの利益を上げたか」を示し、投資家視点での評価に適しています。
一方、ROAは「会社が保有する資産をどれだけ有効に使っているか」を表すため、経営効率の分析に向いています。
まとめ:ROEとROAを使い分けて企業分析を深めよう
ROEとROAはどちらも企業の収益性を評価する重要な指標ですが、視点が異なります。
ROEは株主資本の効率性、ROAは資産全体の運用効率を示します。
両者を組み合わせて分析することで、企業の財務体質や経営効率をより正確に把握できるでしょう。
さらに参照してください: