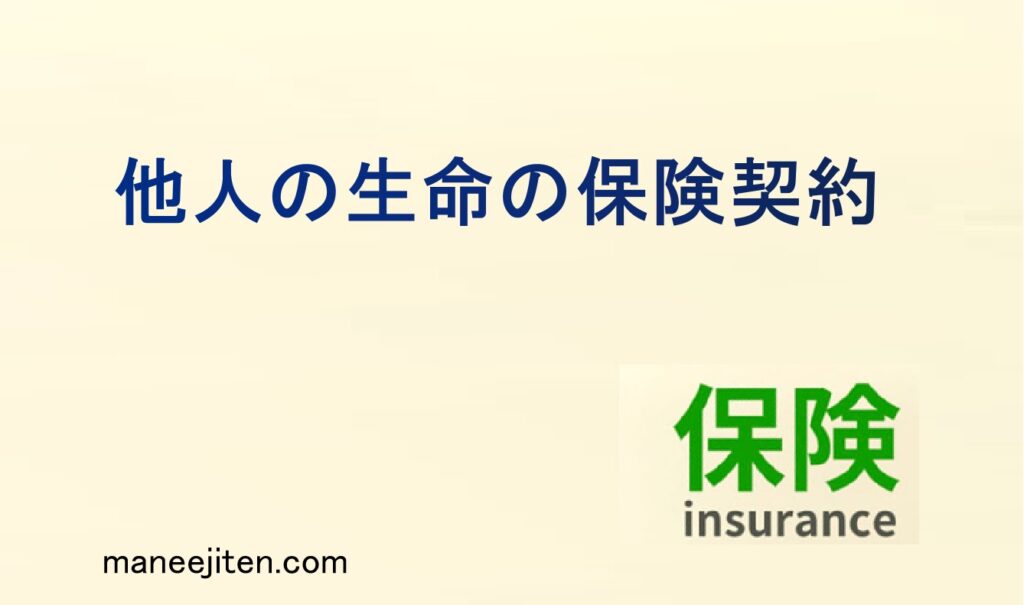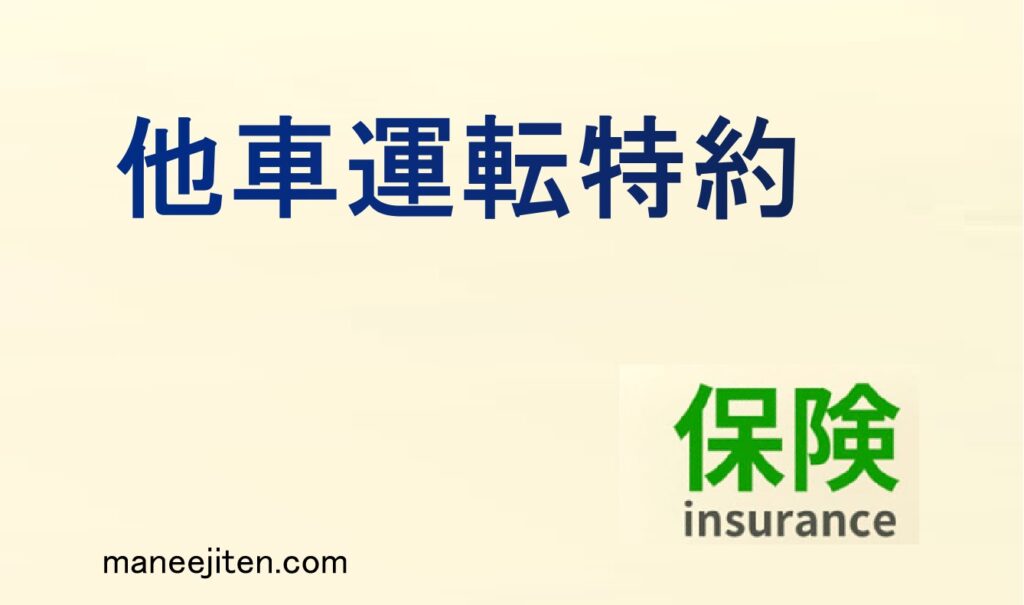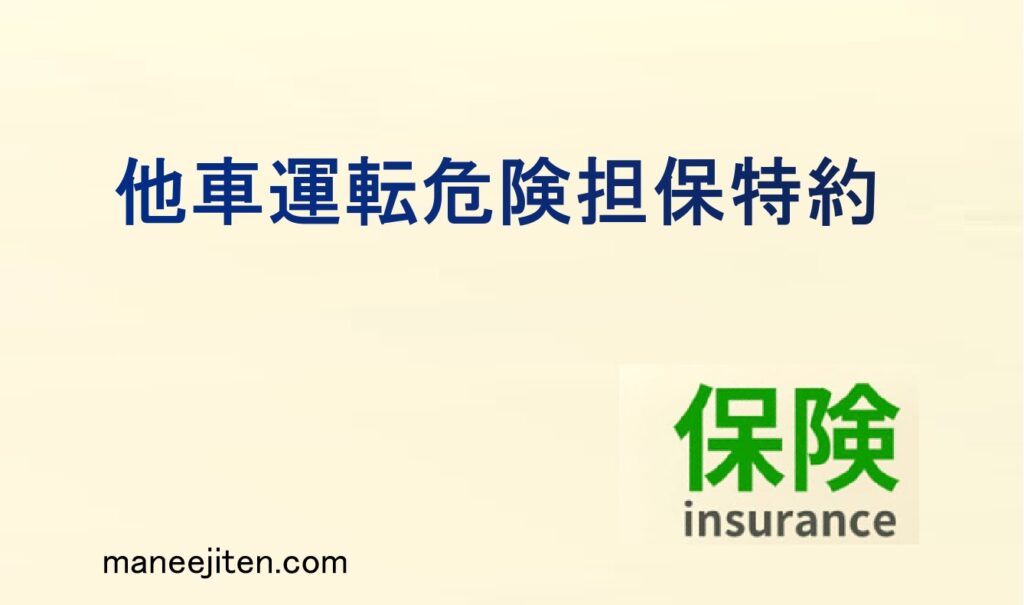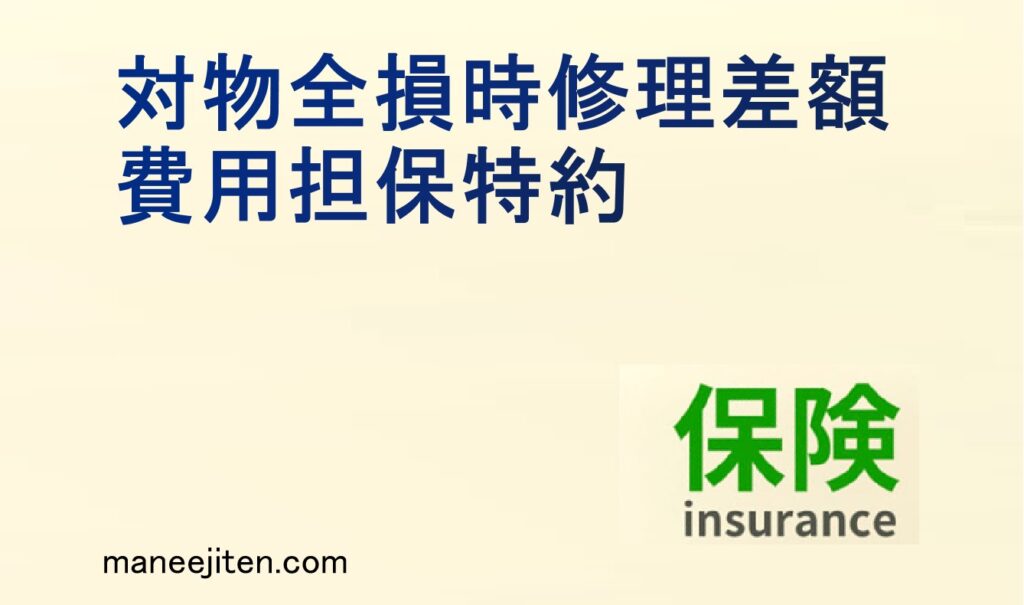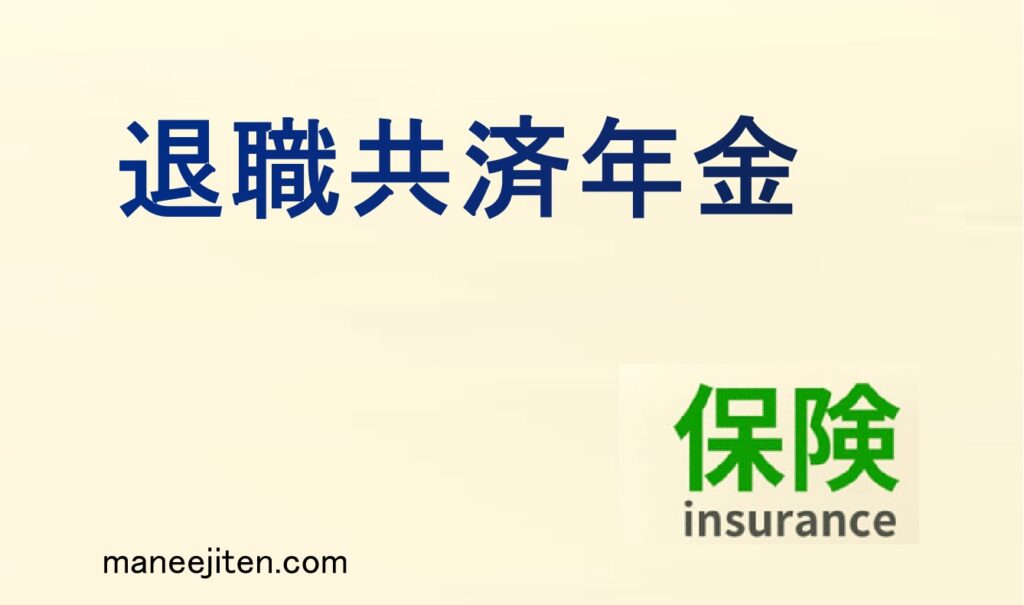他人の生命の保険契約とは?意味・仕組み・注意点をわかりやすく解説
「他人の生命の保険契約(たにんのせいめいのほけんけいやく)」とは、**保険料を支払う人(保険契約者)**と、**保険の対象となる人(被保険者)**が異なる生命保険契約のことです。 一般的な生命保険は、契約者=被保険者となる「自己の生命の保険契約」が多く、万一のときに自分の家族が保険金を受け取る仕組みになっています。一方で、他人の生命の保険契約は、第三者の生命を対象に契約を結ぶ形です。 他人の生命の保険契約の例 例1:夫が妻を被保険者として契約 契約者:夫(保険料を支払う人) 被保険者:妻(生命を対象とする人) 受取人:夫 例2:会社が従業員を被保険者として契約(役員・従業員向け福利厚生)…