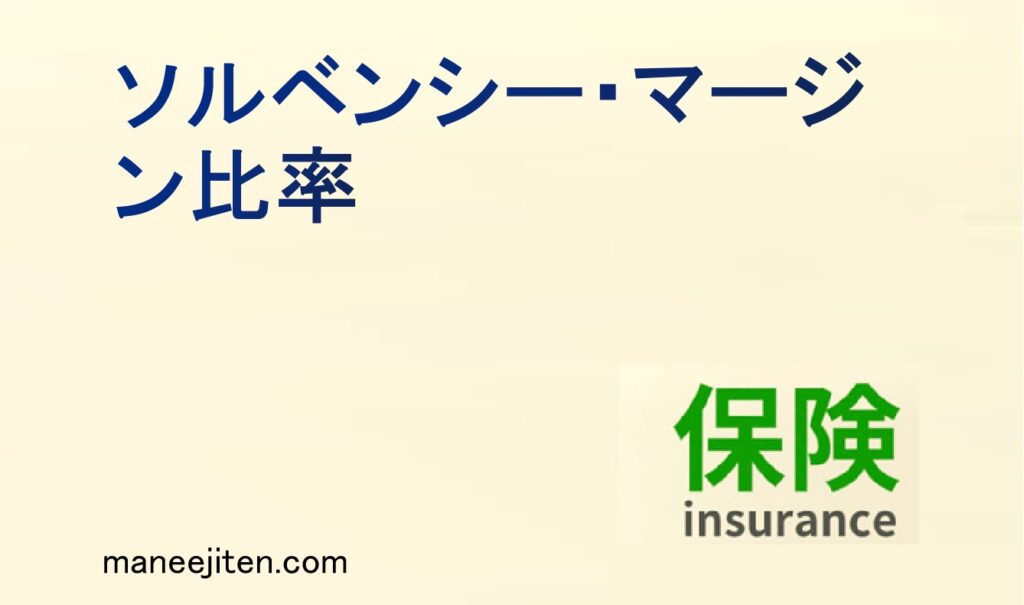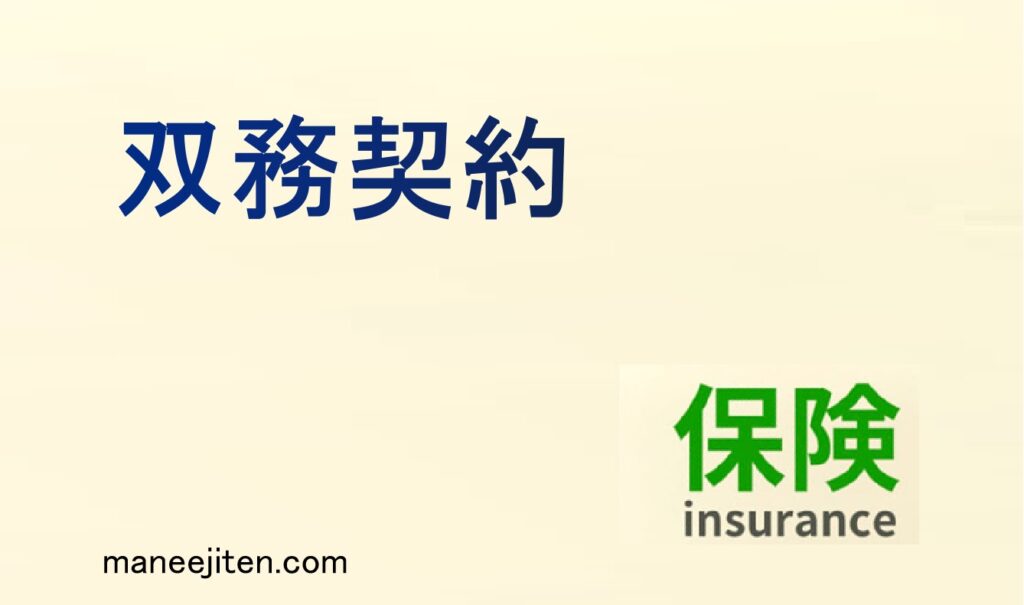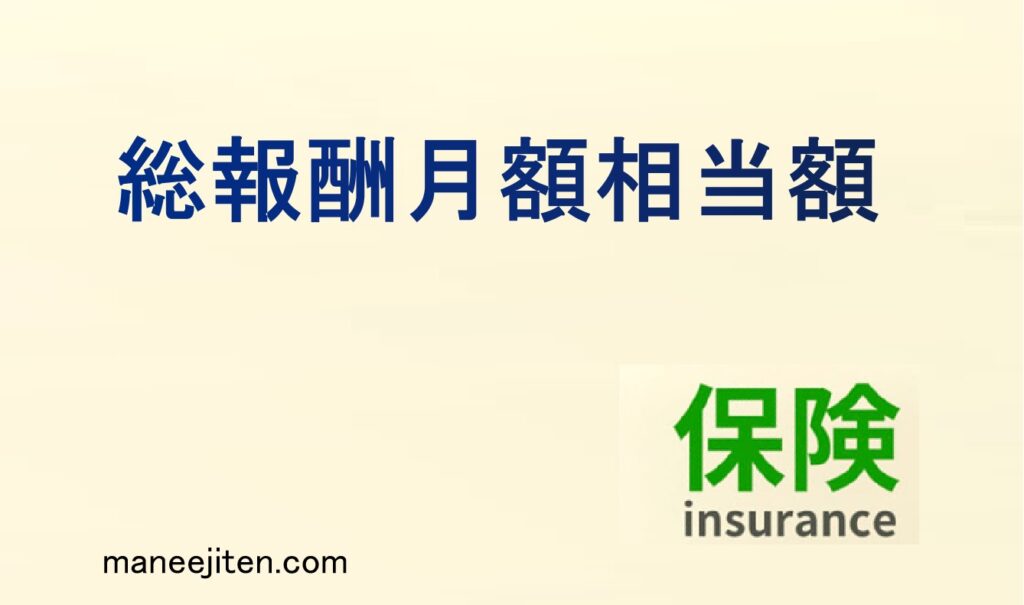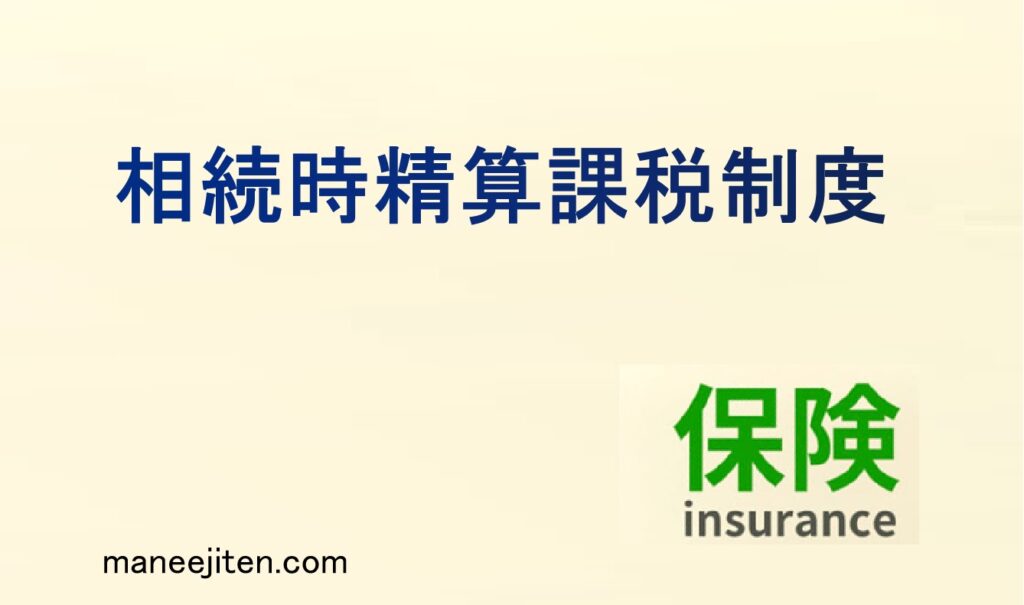損害填補とは?保険金の支払い方式と仕組みをわかりやすく解説
**損害填補(そんがいてんぽ)**とは、保険事故によって発生した損害に対し、保険会社が保険金を支払うことを指します。主に損害保険で使われる言葉で、契約者の損失を一定の条件で補う重要な仕組みです。 この記事では、損害填補の基本的な意味と、代表的な2つの支払い方式「実損填補」と「比例填補」について、具体例を交えてわかりやすく解説します。 損害填補の目的 損害填補は、保険契約者が被った経済的損失を補い、事故前の状態にできる限り近づけることを目的としています。ただし、保険は**「利益を得るためのものではない」**という原則があり、損害額を超える保険金が支払われることはありません。 損害填補の代表的な方式 1. 実損填補(実損填補方式) 実損填補方式では、契約で定められた保険金額を上限として、実際に発生した損害額がそのまま保険金として支払われます。…