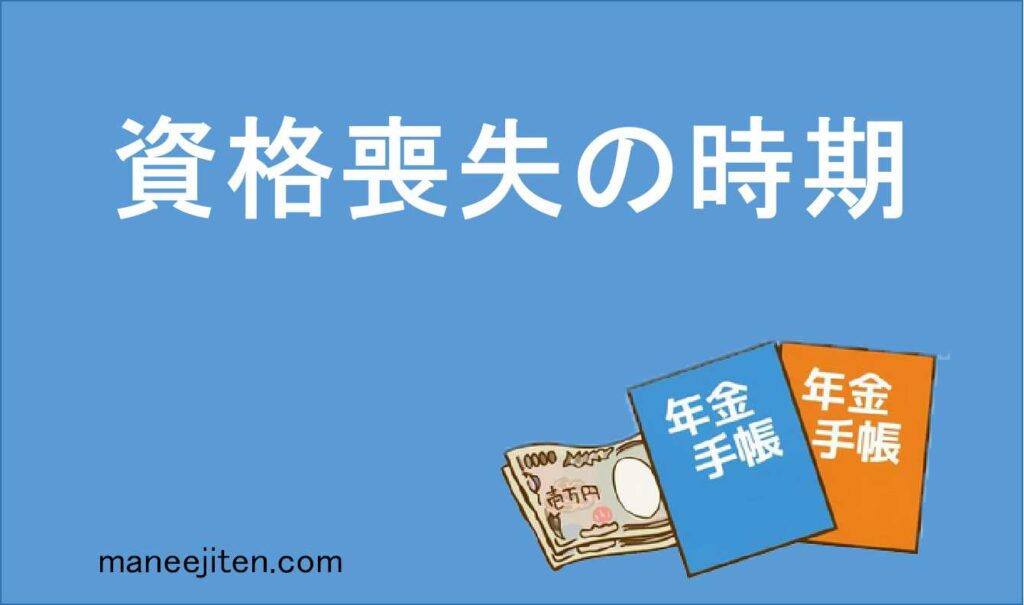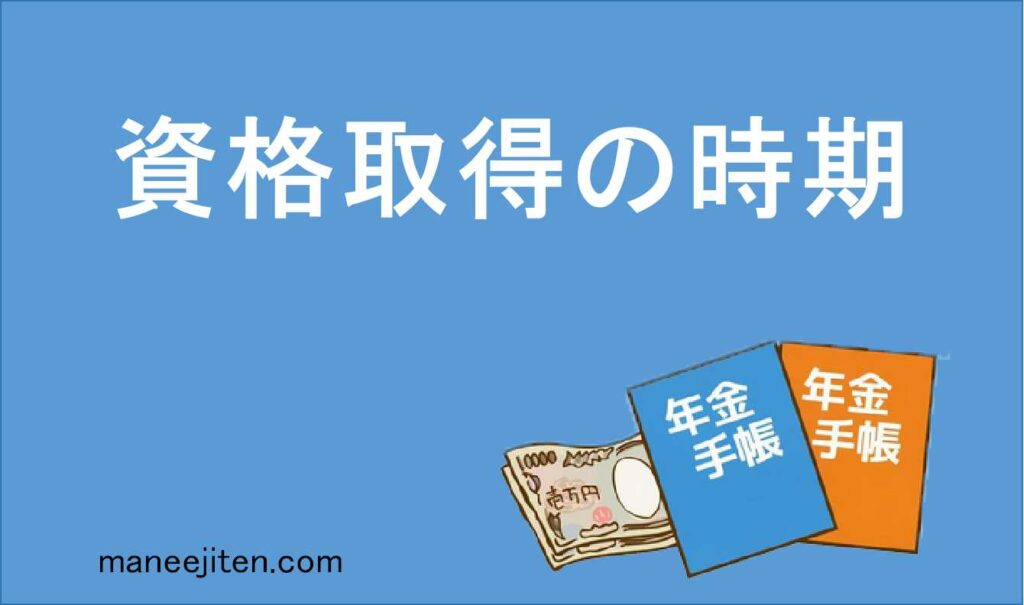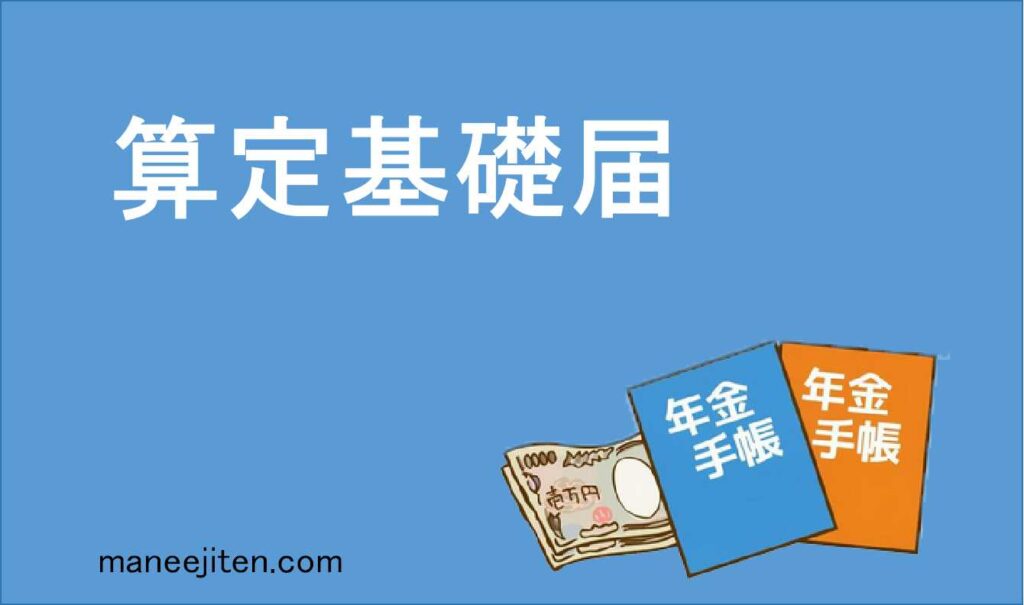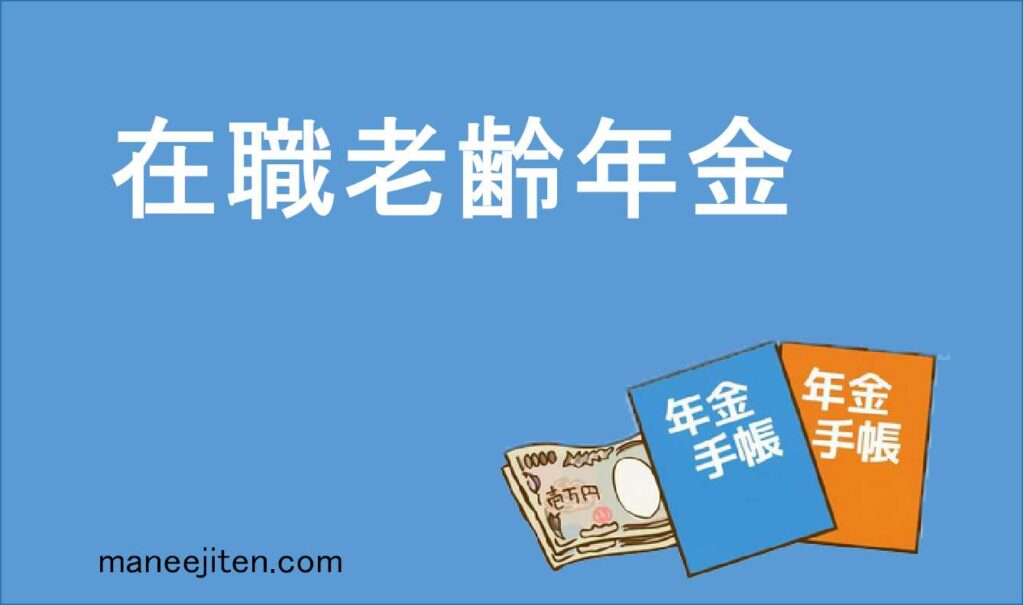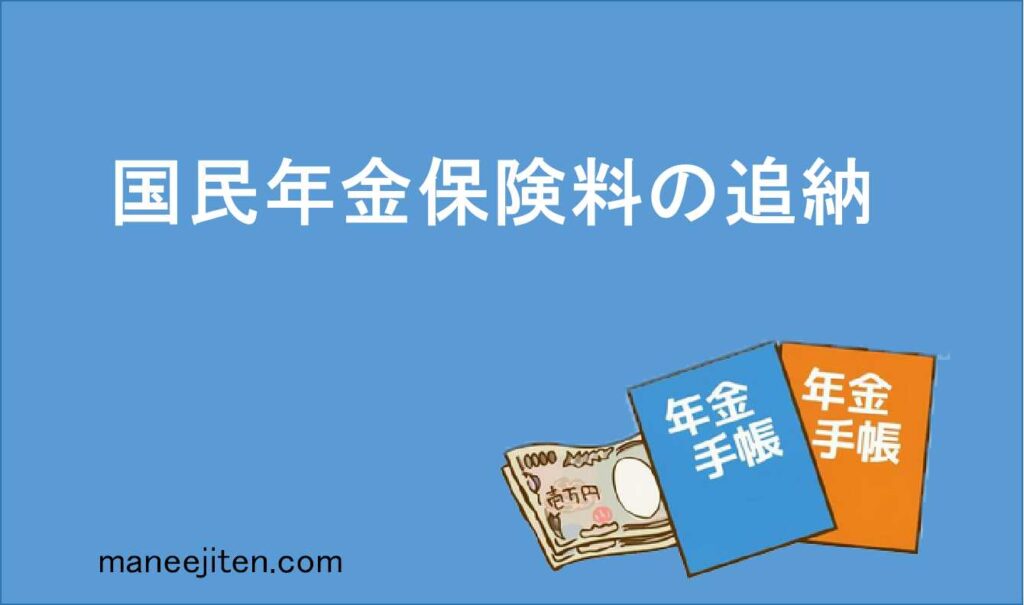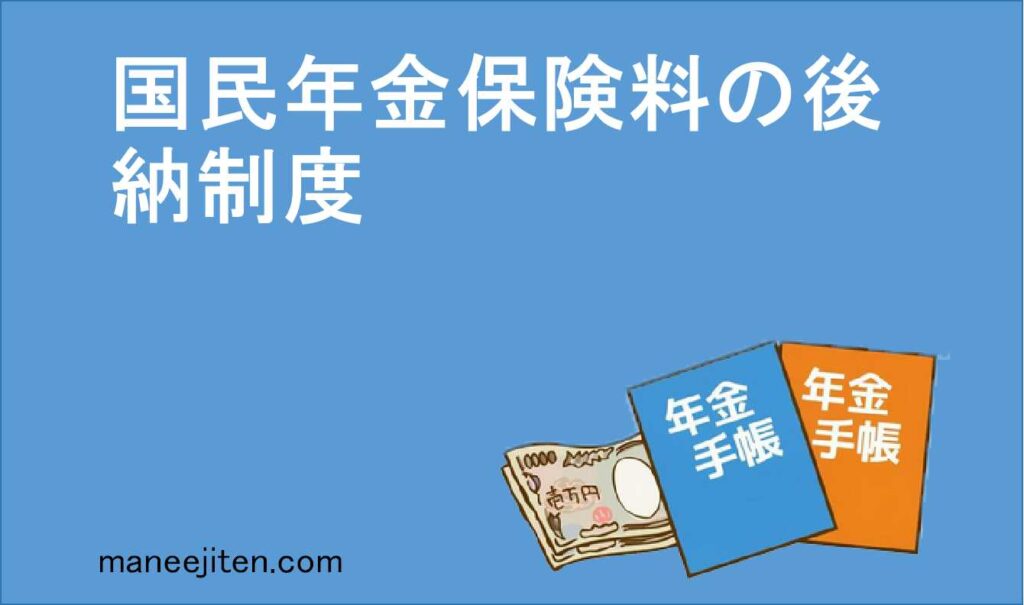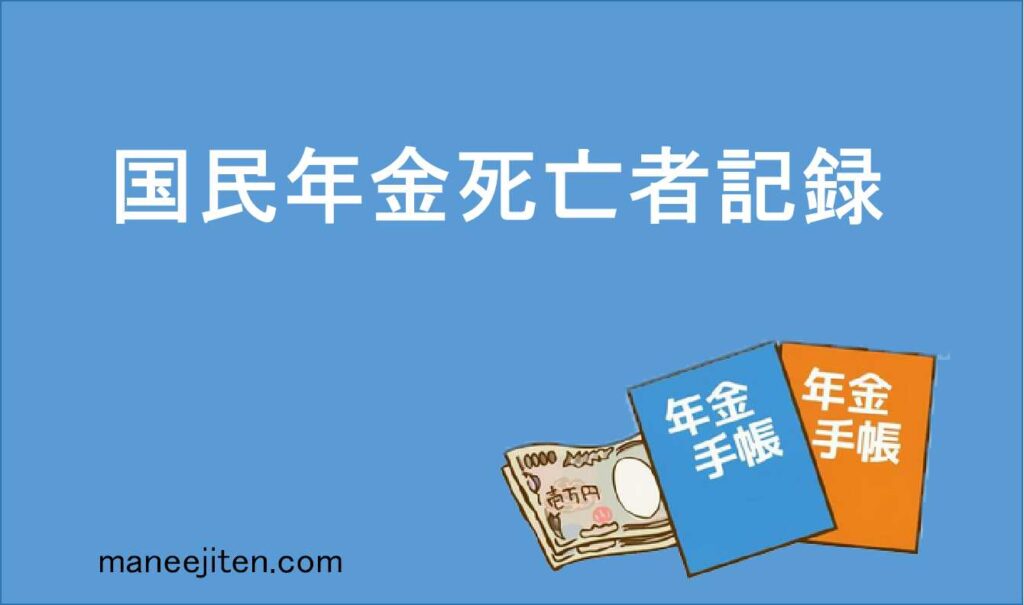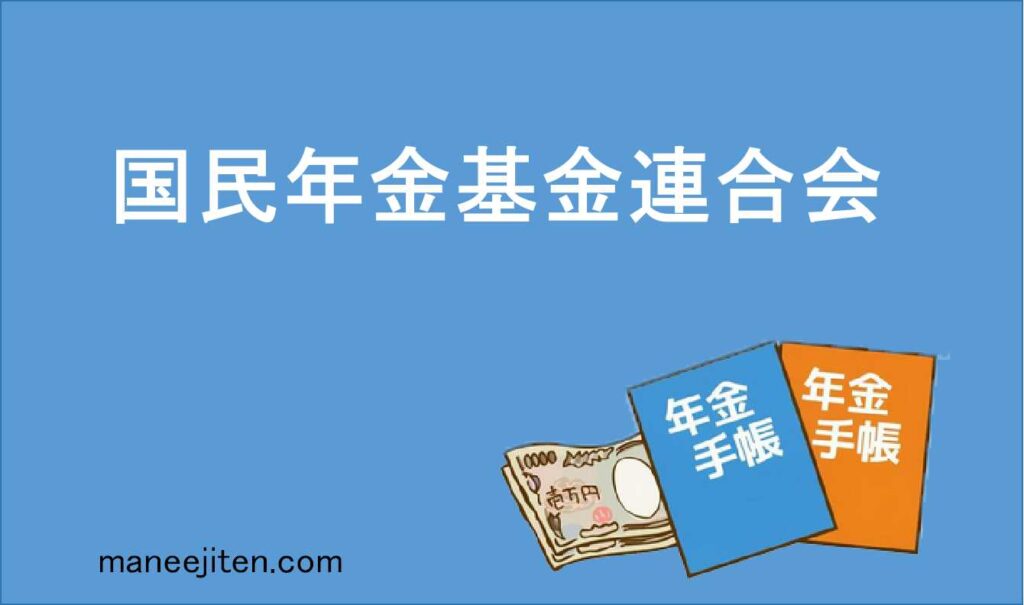時効の援用とは?意味と手続きのポイントをわかりやすく解説
年金や保険、請求権に関わる場面では「時効」という言葉を耳にすることがあります。ただし、時効が自動的に成立するわけではなく、権利を守るためには適切な手続きが必要です。今回は、時効を成立させる手続き「時効の援用」について、具体的な内容と注意点を解説します。 時効の基本 時効とは一定期間権利行使がされない場合に、権利が消滅したり、行使できなくなる制度です。たとえば、年金保険料の請求や給付請求などにも時効が存在します。 自動で成立するわけではない時効期間が過ぎただけでは、時効は自動的に成立しません。権利を守るためには、自ら手続きを行う必要があります。 時効の援用とは 定義時効が成立したことを主張し、権利の消滅を認めさせる行為を「時効の援用」といいます。 手続きのポイント…