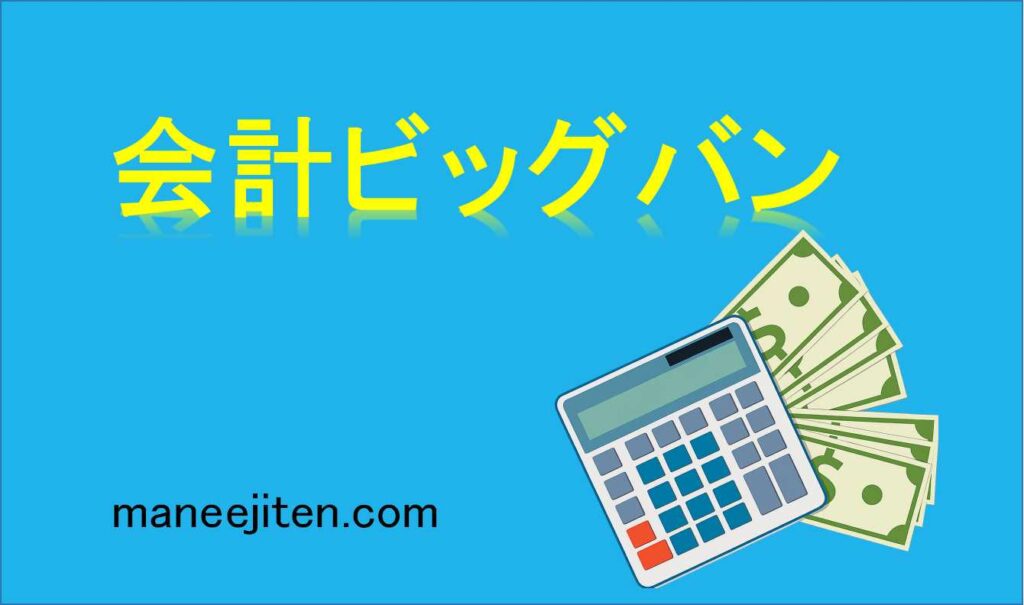借入金とは?勘定科目の意味・種類・仕訳方法をわかりやすく解説
企業が事業を続けるうえで、設備投資や運転資金の確保のために外部から資金を調達することは少なくありません。その代表的な方法が「借入金」です。この記事では、借入金の基本的な意味から種類、仕訳方法、そして経営上のメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。 借入金とはどんな勘定科目? 借入金とは、金融機関や取引先など外部からお金を借りた際に発生する債務を指します。貸借対照表上では「負債の部」に計上され、返済までの間は企業の義務として残ります。 融資を受けた場合、資産である「普通預金」と、負債である「借入金」の両方が増加します。返済時には元本と利息を分けて処理し、利息部分は「支払利息」として営業外費用に計上します。 借入金の主な種類 1. 証書貸付 金銭消費貸借契約証書を交わして融資を受ける方法で、最も一般的な借入形態です。…