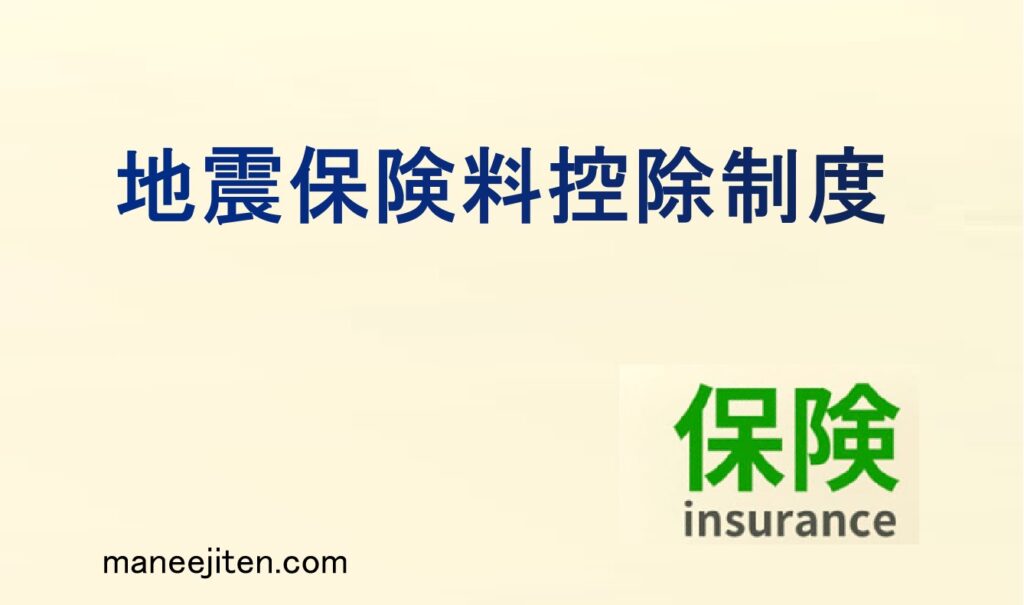地震大国・日本において、自宅を守る備えとして重要な**「地震保険」**。実はこの保険に加入すると、**税金の優遇(控除)**を受けられる制度があるのをご存じですか?
それが「地震保険料控除制度」です。
この記事では、保険の初心者でも理解しやすいように、この制度の概要や背景、具体的な申請方法までをわかりやすく解説します。
✅ 地震保険料控除制度とは?
地震保険料控除制度(じしんほけんりょうこうじょせいど)とは、納税者が支払った地震保険にかかる保険料に対して、所得控除を受けられる制度です。
▼ なぜこの制度ができたの?
2007年(平成19年)1月1日以前は、地震に限らず火災保険や傷害保険なども含む「損害保険料控除」がありましたが、この制度は廃止されました。その代わりに、地震保険に特化した「地震保険料控除制度」が創設されたのです。
🧾 控除の対象となる契約は?
以下のいずれかに該当する保険料が対象になります。
-
地震保険契約(火災保険に付帯されているものを含む)
-
2006年12月31日以前に契約された「旧長期損害保険」のうち、一定の要件を満たすもの
☑ 火災保険だけでは対象外なので注意!
💰 控除額はいくら?
● 所得税の控除額(最大5万円)
-
地震保険料:支払った全額(上限5万円)
-
旧長期損害保険料:支払額の1/2(上限2.5万円)
● 住民税の控除額(最大5,000円)
-
地震保険料:支払った全額(上限5,000円)
📝 控除を受けるには?申告方法を解説
地震保険料控除を受けるには、以下のいずれかの方法で申告が必要です。
▷ 年末調整で申告する(会社員など)
勤務先に「地震保険料控除証明書」を提出すれば、会社側で自動的に処理してくれます。
▷ 確定申告で申告する(自営業・フリーランスなど)
確定申告書に地震保険料控除欄を記載し、保険会社から送られてくる控除証明書を添付(または提示)します。
📌 証明書は毎年10月~11月頃に郵送されるのが一般的なので、大切に保管しておきましょう。
❗ 控除を受ける際の注意点
-
火災保険料のみの契約は対象外
-
保険料を支払った人が控除を受ける必要がある
-
保険の契約者と申告者が一致している必要がある
-
控除証明書を紛失すると申告ができない可能性あり
💡 具体例:どれくらい節税できる?
例:年間の地震保険料 30,000円を支払った場合
-
所得税控除:30,000円分の所得が差し引かれる
-
住民税控除:3,000円が税額控除される(※住民税率10%の場合)
これにより、実質的に数千円単位で税負担が軽減されることになります。
✅ まとめ:申告を忘れず、控除を賢く活用!
地震保険料控除制度は、加入しているだけでは自動で適用されません。正しく申告してはじめて、税制優遇のメリットを受けることができます。
**「うちは地震保険に入ってるけど、申告したことないかも…」**という方は、この機会にぜひ確認を!控除証明書をしっかり提出し、節税対策をきちんと活用しましょう。
さらに参照してください: