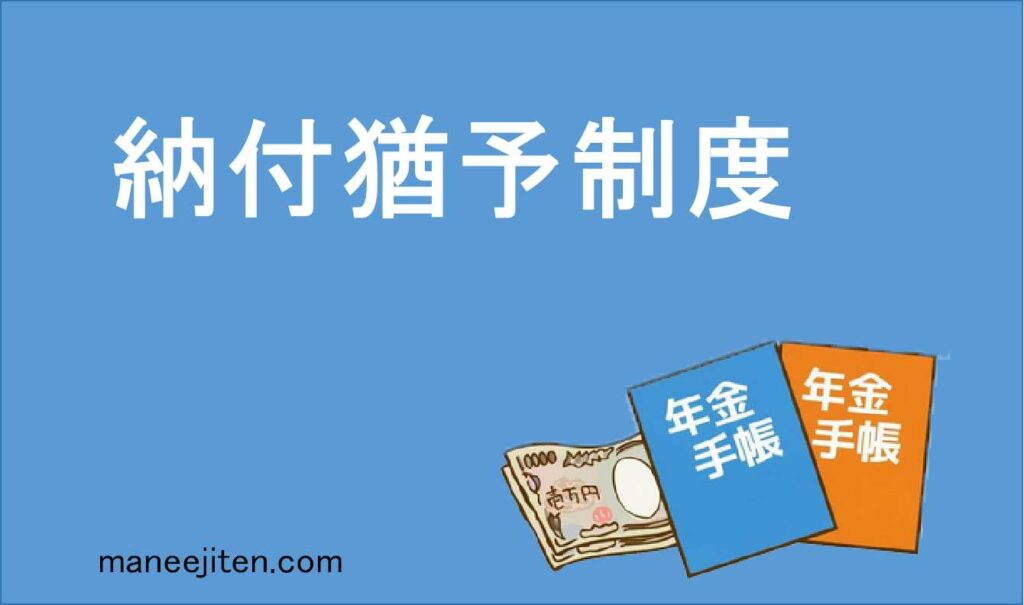「収入が少なくて国民年金を払えない…」そんなときに利用できるのが 納付猶予制度 です。
若い世代の生活を支えるために設けられた制度で、一定の条件を満たせば申請により保険料の支払いを猶予してもらうことができます。
この記事では、制度の仕組みや利用条件、注意点についてわかりやすく解説します。
納付猶予制度とは?
納付猶予制度とは、50歳未満の国民年金第1号被保険者で、本人と配偶者の前年所得が一定基準以下の場合に利用できる制度です。
-
対象者:50歳未満の第1号被保険者(自営業・フリーランス・無職など)
-
条件:本人と配偶者の所得が一定以下(世帯主の所得は不問)
-
仕組み:申請に基づき承認されれば、国民年金の保険料納付が猶予される
この制度を使うことで、経済的に厳しい時期に無理をして保険料を支払わなくても、将来の年金資格を確保できるのが大きなメリットです。
納付猶予期間の取り扱い
納付猶予が承認された期間は、未納扱いにはなりません。
-
受給資格期間に算入される:老齢基礎年金の受給資格を満たすための「加入期間」としてカウントされる
-
年金額には反映されない:追納しない限り、その期間分は老齢基礎年金額には加算されない
つまり、資格期間を確保しつつ、将来の年金額を増やすためには 追納(あとから支払うこと) が大切になります。
追納(あとから払う)について
納付猶予された保険料は、10年間までさかのぼって追納可能 です。
-
追納すれば、その分の老齢基礎年金額が増える
-
追納しない場合は、将来の年金額は少なくなる
「今は払えないけど、将来安定した収入が得られたら追納する」という選択肢があるため、柔軟に考えられるのが制度の強みです。
障害や死亡時の保障
納付猶予期間中に不幸にも障害を負ったり死亡した場合でも、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象になります。
つまり、保険料を払っていなくても生活保障は確保されるため、未納のまま放置するよりは大きな安心につながります。
制度の時限措置について
納付猶予制度は 令和17年6月までの時限措置 とされています。
-
平成28年6月までは「30歳未満」が対象
-
平成28年7月以降は「50歳未満」へ拡大
将来的に延長や見直しが行われる可能性はありますが、利用を検討している方は早めの確認が必要です。
まとめ
-
納付猶予制度とは:50歳未満で所得が一定以下の場合に、国民年金の保険料支払いを猶予できる制度
-
メリット:受給資格期間に算入され、未納扱いにならない
-
注意点:追納しなければ年金額は増えない
-
保障面:障害・死亡時は基礎年金が支給される
-
期限:令和17年6月までの時限措置
「経済的に苦しくて国民年金が払えない」という人は、未納のままにせず 納付猶予制度を活用することが将来の安心につながります。
さらに参照してください: