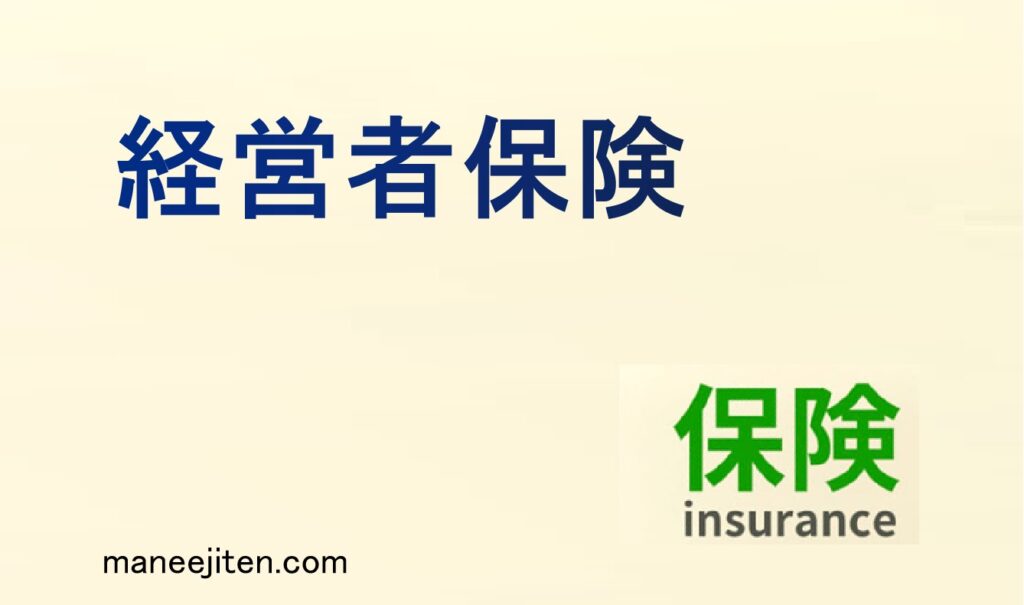企業経営において、万が一のリスクは避けて通れません。特に経営者に万一のことが起きた場合、企業の事業継続に深刻な影響を及ぼすこともあります。
そんなリスクに備えるために活用されているのが「経営者保険(けいえいしゃほけん)」です。
この記事では、法人保険の一種である経営者保険の基本から、導入のメリット・注意点までをわかりやすく解説します。
🔍 経営者保険とは?
経営者保険とは、企業の経営者や役員に万一の事態(死亡・高度障害など)が発生した際に、企業が受ける損失を補填したり、退職金や事業承継に必要な資金を確保したりするための法人保険です。
✅ 基本のしくみ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約者 | 法人(会社) |
| 被保険者 | 経営者または役員 |
| 保険金受取人 | 法人(または遺族、目的により異なる) |
保険料は法人が支払い、税務上も一定の範囲で損金算入できる場合があり、リスク対策と資金準備を兼ねた経営戦略の一環として導入されています。
💡 経営者保険の主な目的
経営者保険は、以下のような場面で企業を支える役割を果たします。
① 万一の事態に備える「事業保障」
経営者が突然亡くなった場合、企業は経営の混乱や信用不安に直面します。保険金によって、以下のような資金に充てることができます。
-
借入金の返済
-
従業員の給与や取引先への支払い
-
一時的な運転資金
② 退職金・弔慰金の準備
経営者が退任・引退した際に支払う退職慰労金や、遺族への弔慰金も、あらかじめ保険で準備しておくことで、企業の財務負担を軽減できます。
③ 事業承継や相続対策
経営者の死亡により事業承継が発生した場合、保険金を使って自社株を買い取るなど、円滑な承継にもつながります。
🧑🏫 具体的なケーススタディ
【事例】中小企業の社長が突然の病気で急逝
金属加工業を営むA社では、代表取締役である社長が急逝。銀行借入2,000万円が残っており、社長の信用によって成り立っていた取引先からも不安の声が。
しかし、A社ではあらかじめ経営者保険に加入していたため、死亡保険金3,000万円を受け取り、借入返済と社員の雇用維持に充てることができた。経営の継続と信頼回復に繋がった。
🧾 税務上の取り扱いにも注意
経営者保険は税務上の扱いが複雑なため、導入の際には税理士などの専門家と相談することが重要です。
主な取り扱いの一例(保険種類により異なる)
-
定期保険(全額死亡保険金):保険料の全額を損金算入可能(条件あり)
-
長期平準定期保険:保険料の一定割合を資産計上し、残りを損金算入
なお、税制改正により取り扱いが変わることもあるため、常に最新の制度をチェックすることが大切です。
✔ 経営者保険の選び方と注意点
導入を検討する際は、以下のような点に注意しましょう:
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 保険金額 | 借入金・退職金などの必要額に見合うか |
| 保険期間 | 経営者の引退時期に合わせて設定できるか |
| 保険料負担 | 会社のキャッシュフローに無理はないか |
| 税務処理 | 最新の税制に適合しているか |
📌 まとめ|経営者保険は“会社を守るセーフティネット”
経営者保険は、企業のリスクマネジメントと資金計画の両面を支える、重要なツールの一つです。
万一のときだけでなく、引退や事業承継まで見据えた**“備え”として活用される保険**であり、特に中小企業にとっては経営の安定性を大きく左右する存在となります。
さらに参照してください:
経過的加算とは?年金の“受給額が下がらない”ための調整制度を解説